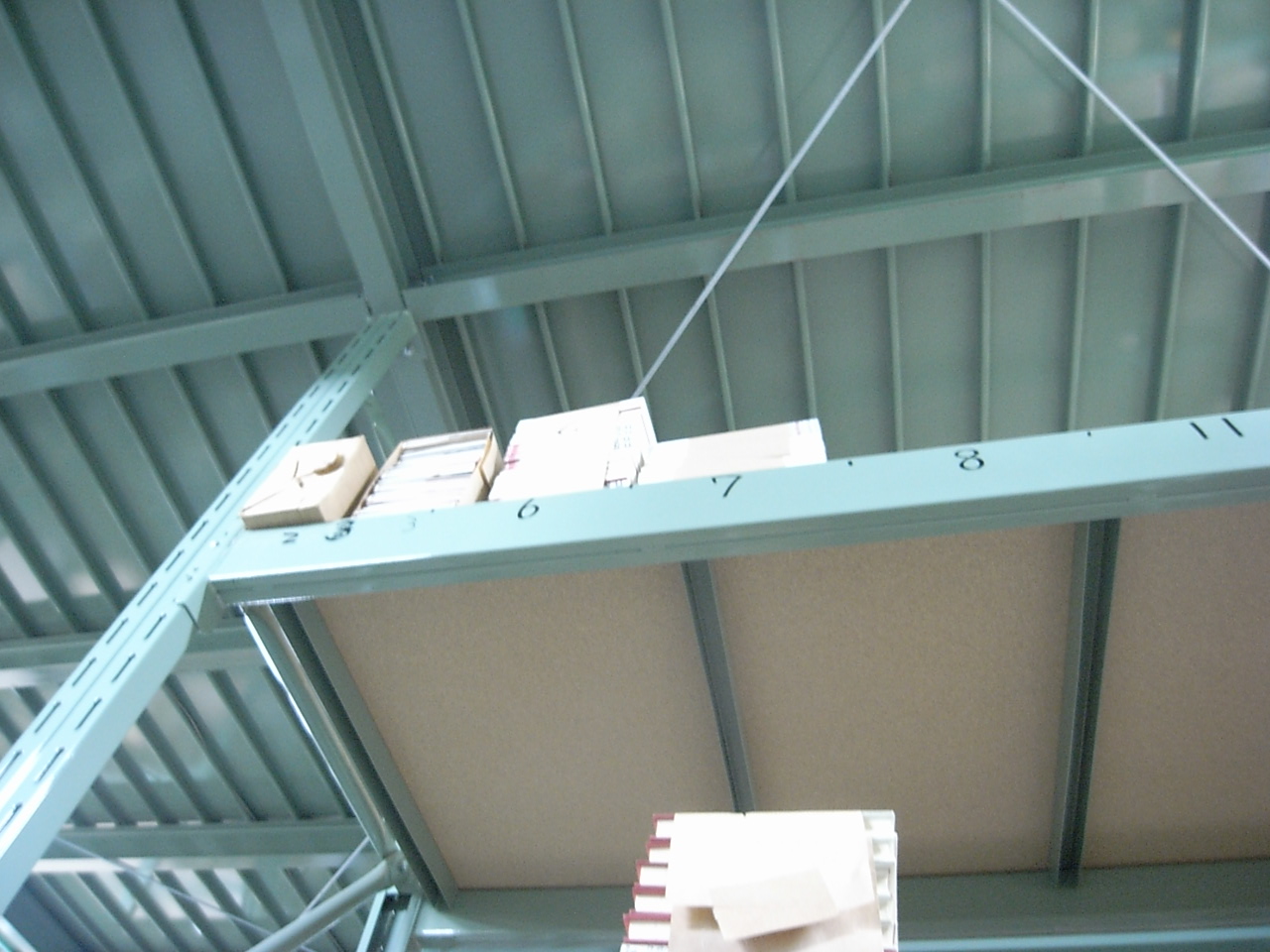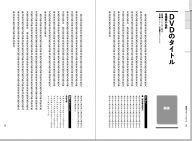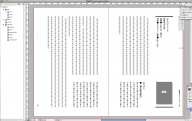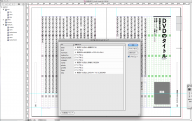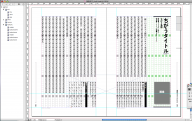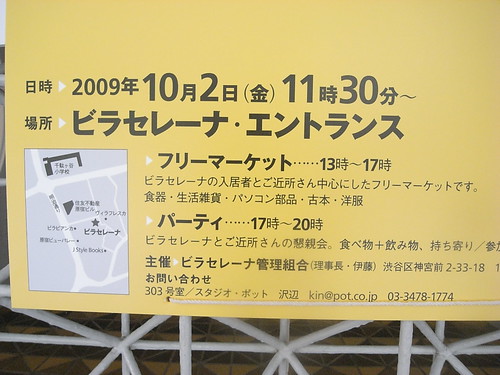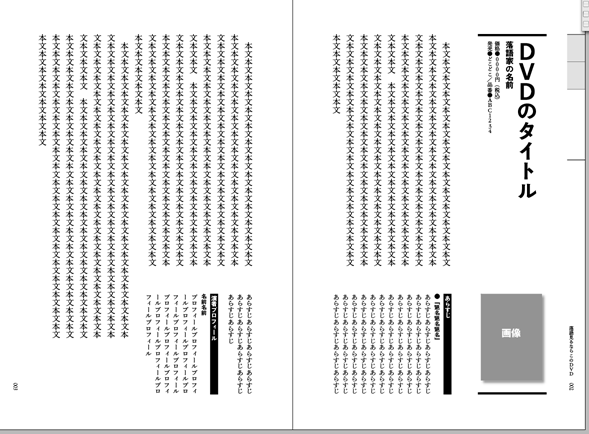ポット出版社長・沢辺均の日記-41[2009.10.05〜06]
2009-10-07 沢辺 均
●2009.10.05月
S社、デザインの打ち合わせ。
その直前、「溜め息に似た言葉」(岩松了)を利用した書店フェア提案をめぐって説教。
狙いのポイントがあいまいなんだな。
「溜め息に似た言葉」は、
脚本家+俳優の岩松了が/「名作」小説からセリフを一つ抜いて/そのセリフのなにがポイントかを書いた、もの。
もう一つは、それに若手の写真を一枚ずつくっつけた。
書店で、その「名作」に岩松了の抜いたセリフと、そのポイントをワンフレーズで、POPを作って、
「名作」自体を売ってもらえないか、というのがフェアの狙い。
でその横に、この「溜め息に似た言葉」も、、、、。
なのに、肝心のPOPの見本がない、とか、いろいろ。
●2009.10.06火
昼飯を食いながら、佐藤と打ち合わせ。
もどって、取材を受ける。
夕方はNext-Lの原田さん、田辺さんが来て、取材+ビデオ。
その後、均整(整体の一種)。
当社会長・飯島洋一と、均整の合間に雑談。
飯島は、井筒和幸監督の新作「ヒーローショー」に出演していて、
井筒監督の演技指導の厳しさの話がおもしろい。
映ってないところの人にまで、本気で演技させるとか、、。
図書館大会で原田さんたちが発表するときのネタだそうだ。
夜は、社内に出した課題についての「解答」を書く。(課題はマエの日誌に書いた)
↓は私が書いたものです。
──────────────────────────────
●炭素と溜め息のシナノの印刷請求をみて、四六版で192ページと同じなので、
なぜ費用が2倍以上の開きがあるのか、を箇条書きでかけ。
・プリントは各自の机に置く
・参加は自由/提出後参加者には解説をします
・箇条下記には、その数字的な根拠を示せ
沢辺の解答(請求書では399000溜め息が高い、下記計算合計は390006)
○本文、炭素はモノクロ、溜め息はオール4色だから
・色校の有無 0円/96000円 溜め息が96000高
・刷版 (1/1×3)=6版/(4/4×3)=24
単価はかわらず2500円
額で、15000円/60000円で 溜め息が45000高
・印刷 (1/1×3)2000s=6版/(4/4×3)2000s=24
単価は 5000円/5500円
額で、30000円/132000円で 溜め息102000の差
○カバーとオビ、炭素は付け合わせ、溜め息は別刷のため製版+印刷+ニス、が費用の上乗せ(用紙別)
・製版代(色校含む) 2×8000=16000/2×5000+2×4500=19000 溜め息が3000高
・刷版印刷(四六半裁3面1334s/? 1000s) 2×7000=14000/2×7000+2×7000=28000 溜め息が14000高
・ニス引き 1334×15=20010/1×7000+1×7000=14000 炭素が6010高
○表紙の刷版印刷、理由は解らんけど、溜め息の単価が1000円高
○表紙をニス引きにして、溜め息7000円高
○製本が、並製/上製で 2000×24.45=48900/2000×61.35=122700 溜め息73800高
○配本料 理由不明で、25000/20000 炭素の5000高
○用紙類
・本文 使用枚数が1色/4色で、予備の紙に差がある 6750/7500
キロ単価 130/160
で62775/90000 溜め息27225高
・カバー+オビの付け合わせのため(単価はほとんど変わらず)
紙 800枚/700+700枚 金額 47080/40810+28721=69531 溜め息が22451高
・上製のため、ボール紙が溜め息に必要 0/150×63.3=9540 溜め息が9540高
──────────────────────────────
Comments Closed