 |
 |
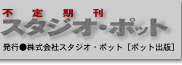 |
| | ▲部屋top | 部屋[番外26] | 部屋[番外25] | 部屋[番外24]| 部屋[番外23] | 部屋[番外22] | 部屋[番外21] | 部屋[番外20] | 部屋[番外19] | 部屋[番外18] | 部屋[番外17] | 部屋[番外16] | 部屋[番外15] | 部屋[番外14] | 部屋[番外13] | 部屋[番外12] | 部屋[番外11] | 部屋[番外10] | 部屋[番外9] | 部屋[番外8] | 部屋[番外7] | 部屋[番外6] | 部屋[番外5] | 部屋[番外4] | 部屋15 | 部屋14 | 部屋13 | 部屋12 | 部屋11 | 部屋10 | 部屋9 | 部屋[番外3] | 部屋8 | 部屋7 | 部屋[番外2] | 部屋[番外1] | 部屋6 | 部屋5 | 部屋4 | 部屋3 | 部屋2 | 部屋1 |怒り心頭の部屋 | |
| 真実・篠田博之の部屋[番外13] | [2001年1月19日] |
| 真実・篠田博之の部屋 [番外13] |
前々から言っているように、主語を「私」にできない人たちがたくさんいます。一方で、わざわざ自分を出すべきではないところで「私」を強調する人もいます。前回まで書いてきたように、実は、どっちも根っこは一緒で、「私」と「他者」が曖昧になっているためなのではないかと疑うわけです。 例えば、相手の名前をしっかり出した上でのインタビューというのは、あくまで相手を立てる仕事だと私は思っています。どうしたって聞き手のキャラや主張も反映されるものですけど、聞き手は黒子であり、黒子の範囲で技量を出すべきです。相手の言いたいことを引き出して、言葉をよりよくまとめることに最大の技量が発揮され、読者は聞き手ではなく、語り手の存在のみを意識する。読み手のほとんどは「このインタビュアはすごいな」ではなく、「この人って、面白いことを言うな」という印象のみを受ける。ライターや編集者、あるいはインタビュイ(インタビューされた人)だけが、インタビュアの技量に気づく。そういうもんだと思うのです。 何が嬉しいって、『熟女の旅』を読んで、「長田長治ってすごい人ですよね」なんて言ってくれる人がいることです。札幌の風俗妻である「マットdeイッてミルク」の朱里ちゃんは、本はロクに褒めずに、「長田さんのファンになりました」と言っていて、私としてはシメシメです。『風俗就職読本』における竹子ちゃんも同様です。ここで私が主張しては元も子もないかもしれませんけど、竹子ちゃんや長田長治という素材からから言葉やキャラを最大限を引き出して、私の存在を意識させずに、彼らの存在を際立てる技量が発揮されているってことです。 ところが、インタビュイの存在を利用して、インタビュアが前面に出て自己主張するようなインタビューって多くないですか。しかも、それがいいインタビューだと誤解している人がいる。誰がインタビューされていたのかもわからなくなって、インタビュアの思い込みたっぷりの地の文章のみが印象に残ったりして、黒幕が黒幕としての自己主張をしたら黒幕ではなくなるように、インタビュアがインタビュイより目立とうとしてどうするって話です。 書き手を出すべき原稿ではないのに、自己主張が過ぎる原稿を書く人って多いような気がするのです。無署名の原稿なのに、「私」って主語を書いてきたり。無署名なんだから、「私」なんてないんですよ。主語があるとすれば「本誌」とかになるんでしょう。無署名原稿の責任主体は編集部であり、書き手個人ではないんですから。新聞のベタ記事で、「私が夜討ちで担当取り調べ官から無理矢理聞き出したところによると、犯人は17歳の少年で」なんてことを書かないですよね(全部署名にして、こういう新聞記事にする手もあると思いますけど)。 * その一方で、「私」と書くべきところでは書かない。これは自己主張しない、というのではなく、他者の主語を借りて依存した上で、自己主張するという意味では、インタビューて聞き手が自己主張しようとするのと、実は同じことなのてはないか。 これについては『魔羅の肖像』で詳しく述べてますし、『ワタ決め』にからめても「黒子の部屋」で書きましたけど、自分が体験しただけの話、自分が感じただけの話に過ぎないのに、なぜか主語が「男」になり「女」になり「我々」になり「日本人」になり「人間」になってしまうのです。「いつからおめえの会社になったんだ」という感想と同様、「いつからおめえが人類を代表するようになったんだ」という話です。 いつになったら出るのかわからぬ『風俗嬢意識調査報告』ですけど、あの調査で、売春の是非を聞いた質問(ここでは個人売春のみを指します)に対する答えが非常に興味深い。是非はおよそ半々だったのですけど、売春を是とした答えのほとんどは「やりたい人はやればいい」といった、まさに性の自己決定権を体現するような答えになっているのに対し、非とする人は「危険」ということを挙げていて、売春自体の是非とは本来関係のない答えでありまして、また、「自分ができない」という個人的な事情を書いているものが多数紛れ込んでいました。 『売る売ら』で宮台さんが言っていたように、「自分自身できない」「私は嫌」というように、自分ができるか否か、自分が好きか否かと、社会的規範をどう考えるかの区別ができない人があまりに多い。「あなたの妻や娘が売春していて許せるのか」と恥じることなく公然と言ってのけた大阪弁護士会の呆れた女性弁護士も同様です。自分が感じていることは自分の感じ方でしかないかもしれない、それが他人には通じないかもしれないという想像が働かない人がいるのです。 この際に、それがどれだけ個人的であり、特殊なものでしかないとしても、「私はこうだ」と言うのはいい。ちゅうか、こういう個人こそが自分の体験や考えを自分の体験や考えとしてどんどん晒すべきと思ってます。 しかし、自分の発言を自分一人で受け止められない人たちがいて、こういう人たちは往々にして、主語を曖昧にしてしまう作業を恐らくは無意識にしてしまうのでしょう。 「唐沢俊一とはどうなったのか」と聞かれて思い出したのですけど、唐沢俊一もそうでしたね。「オレはこう思う」という話でしかないのに、「書き手はこうだ」「編集というのはこうだ」「読者はこうだ」と言ってしまう。一体いつからこの人は「ガロ」の書き手、編集、読者の意思を代弁する人になったのかと失笑したものです。 * このような同一視を批判する対象にも投影することがあります。例えば、その相手が社長の場合、社を代表する人ですから、会社全体を否定することもありましょう。しかし、一編集者が何か問題を起こしたところで、その会社全体を否定するには至らない。これが二人三人と続いた場合は、会社の方針であったり、会社全体に浸透した体質なのかもしれないと初めて思う。 篠田氏についても、私は当初、創出版全体の否定なんてするつもりは毛頭ありませんでした。編集長にして社の代表であり、かつ小さな会社なのですから、篠田氏と創出版を同一視してもかまわないでしょうが、現に私はそうしていませんでした。しかし、篠田氏によれば、私の投稿をひねり潰したのは、編集員全員の合意だそうですから、私は編集部全体を批判していくしかなく、編集員全員が、著者の権利を軽視し、反論権を認めず、ギャラをごまかし、訴訟を起こすなどと恫喝して言論を潰そうとするような人達だと判断しています。 現実には、一編集員が編集長に楯突くことは難しく、それ以前に自分の意見をしっかりもっている編集者なんてほとんどいませんから、判断が下せないでいるということだけなんでしょう、たぶん。あるいは、何の興味もないか。そう思いつつも、篠田氏の言うことに何ら反論もしていない以上、私は彼らをも批判するしかない。 ここで篠田氏が書いてきたことが大変に参考になります。 永江朗氏は敬意を払える仕事をしている人物で、同世代の書き手としては、数少ない共感を抱ける部分の多い人です。それであっても意見の齟齬があるのは当然で、青林堂をめぐるゴタゴタに対する評価も違いますし、本多勝一と岩瀬達哉の論争に対する評価も違います。篠田氏は、私が後者のテーマについて永江氏を批判しただけで「敵対している」と解釈します。 あらゆる点において意見が合致していないと、敵対しているということになるのなら、私は全人類と敵対しているでしょう。 もちろん、篠田氏と私は、互いに人間性の否定、存在の否定にまで至っておりますから、これを「敵対」と表現することに異論はないですよ。小林よしのりだって、かなりまで敵対してますし、唐沢俊一も同様。 それでもなお、「創」という雑誌は存在していてもいいと思っていますし、既に書いたように、小林よしのりのある部分については評価しないではない。「ゴー宣」の初期はやっぱり面白かった。「おぼっちゃまくん」の再放送もたまには見ます。「あんなもんを放映するな」なんてことは決して言いません。唐沢俊一の仕事って、よく知らないので、どこを評価していいのかわかりませんけど、なんか評価するところがあるかもしれません。 宅八郎と「DSJ」のトラブルにおいて、私は宅八郎を批判する立場にあり、このトラブルにおいて宅八郎のとった行動により、過去に溯って宅八郎の行動のいくつかについても疑問が生じたところがありますが、それでも、宅八郎がやってきたことで、今も支持していることは多数あります。 ところが、小林よしのりは、自分を批判した人、自分が批判した人に対する評価は見事に全否定になります。宅八郎に対しても、かつては好意的な書いていたり、私の原稿を評価したコメントを「ゴー宣」の欄外に書いていたものですが、そういう過去を平気でなかったことにしてしまいます。 これと同じ発想ですけど、竹内義和は、私への反論として、私が与り知らぬ宅八郎の行動を取り上げるという愚かな真似をしていたことがあります。「そんなこと、私の知ったことではありません。直接宅八郎に言ってください」でおしまい。この人もまた宅八郎のある言動を支持した人間は、宅八郎の言動のすべてについて責任を取らなければならないと考えているらしいのです。竹内義和が指摘していた宅八郎の行動が事実として(事実じゃないと宅八郎は言ってましたけど)、それに私が批判的だとしたところで、相変わらず、私は宅八郎のある言動を支持することがあっていいわけです。竹内氏というのは、そうもあらゆる局面において正しいことばかりやっている自信があるのかな。 私の中にもこういうところがないわけではなく、人間性に関わってくる言動を批判する時には、容易に全否定に至りがちではあります。篠田氏との関係で、ここに足を踏み入れた第一のきっかけは、議論をせずに、食事で懐柔しようとしたことであり、あれ以来、あるテーマについての意見の相違ではなく、マスコミ人として否定するようになっていきます。要するに言論の放棄ですからね。 小林よしのりについても、私が許せなくなったのは、言論を放棄して、裏で宅潰し、つる師潰しを図ったことにあります。こうなったら、もう人としての否定をするしかないでしょう。 人としての否定をしてしまうと、今度は、その人物が何を言おうと、「何言ってやがる」になりがちです。家族を殺した犯人が、どんなに偉そうなことを言おうとも、また、それ自体、どんなに正しい内容だったとしても、「何言ってやがる」になるのと同様です。自分の家族を殺した犯人であっても、一方で、世界的な発明をしたり、素晴らしい小説を書くことはあるわけで、人を殺した罪とは別に、そのことを評価したっていいのですけど、当事者としては、なかなかそうはならんものでしょう。 それでも、私は過去を改竄することにはためらいが生じ、「過去は評価していたが、今は違う」でいいと思っています。まして、単なる意見の相違であるなら、「ここは評価できるが、あちらは評価できない」といったように物事も人間も是々非々でいいのです。 篠田氏が、誌面で個人批判することを好まないのは、第一には、「意見の相違=敵対関係」としか見られない狭量さにあります。しかし、これは篠田氏に限らないことであり、私の中にも十分ある傾向です。次回このことを見ていきます。 |
| ←真実・篠田博之の部屋topへもどる | page top ↑ |