 |
 |
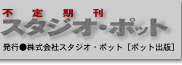 |
| | ▲部屋top | 部屋[番外26] | 部屋[番外25] | 部屋[番外24]| 部屋[番外23] | 部屋[番外22] | 部屋[番外21] | 部屋[番外20] | 部屋[番外19] | 部屋[番外18] | 部屋[番外17] | 部屋[番外16] | 部屋[番外15] | 部屋[番外14] | 部屋[番外13] | 部屋[番外12] | 部屋[番外11] | 部屋[番外10] | 部屋[番外9] | 部屋[番外8] | 部屋[番外7] | 部屋[番外6] | 部屋[番外5] | 部屋[番外4] | 部屋15 | 部屋14 | 部屋13 | 部屋12 | 部屋11 | 部屋10 | 部屋9 | 部屋[番外3] | 部屋8 | 部屋7 | 部屋[番外2] | 部屋[番外1] | 部屋6 | 部屋5 | 部屋4 | 部屋3 | 部屋2 | 部屋1 |怒り心頭の部屋 | |
| 真実・篠田博之の部屋[番外12] | [2001年1月18日] |
| 真実・篠田博之の部屋 [番外12] |
内容について同意するか否かを別にして、あるいはそれ以外の点において同意するか否かを別にして、名指しでの批判をガンガンやらかす田中康夫、小林よしのり、呉智英、佐高信とかって、偉いと思ったりもします。 名指しの批判をすることによって、仕事を干されたり、仕事をする範囲が狭くなるという考えをする人もよくいます。というか、公の場では名指しの批判をせず、飲み屋で延々と同業者や編集者の批判をやっている人たちは、たいていこれでしょう。 こーんだけ私が名指しでの批判をやってきて、それでもとりあえず仕事はやり続けられているのですから、仕事を干されることって皆さんが恐れているほどはないとは思いますよ。その出版社なり編集者個人なりを批判したことによって仕事を失ったのは、今まで「創」だけじゃないかな。そう疑わしきことは何度かありますけどね。 ある編集者を名指しで批判したところで、同じ編集部の別の編集者が仕事を依頼してくることはいくらでもありますし、ある雑誌をボロクソに書いたところで、同じ出版社の別の雑誌が依頼してくることもよくあります。何も考えていないっちゃいないんですけど、健全と言えなくもない。 自分がサラリーマンだった時代のことを考えたって、会社や同僚のことをボロクソに言う人がいたところで、その通りだと思えば「その通り」と思うだけでした。もちろん、筋違いの批判であれば、「何言ってんだ」と反発もしましょうが、私が所属していた会社の社長の発言について批判をしている物書きの話を聞いた時に、「ここの社長なら、そういうことを言いかねないからな」と思い、その物書きに好感を抱いたこともあります。そんなもんです。 でも、やっぱりサラリーマンの中には、その内容の如何を問わず、「うちの会社のことを悪く言うとはけしからん」と思う人もいることでしょう。「うちの会社」だなんて、自分が所属している組織と自分を同一視する人たちはどこの世界にも少なからずいるもので、出版界にだって当然いるでしょう。となると、そういう人たちからの仕事は来なくなるかもしれませんね。でも、こういう人たちから仕事が来なくてもいいじゃないですか。最後は会社の立場を代弁するだけで、決して責任なんてとってくれませんからね、こういう人たちは。 前回紹介した高木仁三郎著『原発事故はなぜくりかえすのか』(岩波新書)では、自己を埋没させると同時に、公益性が欠如した原子力産業・原子力行政を強く批判しており、書評でも触れたことですが、非常に興味深いエピソードが書かれていました。 『原子力工業』という原子力推進派のいわば業界誌があって(現在は『原子力eye』と改題)、ここに掲載された論文を高木氏が調べたところ、7割が「我が国は」で始まると言います。つまり、「我が国の電力事業は」といったところから文章を展開するのです。また、残りの3割の論文もすべて、このフレーズをどこかで使っているそうです。 このことは、原発そのものの危険性、安全性を論じるのでなく、電気事業においての原発の必要性から説いて、原発を肯定していくしかないという彼らの事情も反映されているのでしょうけど、黎明期の原子力産業内部にいた体験から、高木氏はここに原子力産業・行政の体質が如実に表れていることを見抜き、これが例の「議論なし・批判なし・思想なし」の「三ない主義」の体質につながっていること、あるいは原子力に限らない日本の産業全体、行政全体につながることをも示唆します。 ガンと闘いながら病床で語った録音テープをまとめた本のため、もはやそれ以上論ずる猶予はなかったのでしょうけど、日本人論というべき領域にもいくらか入り込んでいて、「我が国」という言い方について、もうひとつ高木氏はエピソードを紹介しています。 国際会議の場で、日本の大使館員がプルトニウム政策についての釈明を求められたのですが、この大使館員は自分では答えられない。自分の意見を言えばいいものを、本国に問い合わせるとして翌日に回答を伸ばします。その翌日、ありきたりの日本の公式見解を説明するのですが、その際に「MY COUNTRY」と日本を表現して、その場にいた人達の失笑を買ったそうです。 「我が国」の直訳です。英語の機微がよく私にはわからないのですが、高木氏の言うように、こういう場合は「JAPAN」とすべきであり、王様でもないのに「MY COUNTRY」はおかしく、アメリカの大統領が演説する際にも、「THIS COUNTRY」と表現するという指摘は、そうなんだろうなと理解できます。高木氏は実際に聞いたわけではないのですが、仮に大統領が言うことがあるとしても、「OUR COUNTRY」だと言います。 日本語で言う「我が国」の「我が」は、ニュアンスとしては「我々の」を含んでいて、日本国内においても、「私の国」「うちの国」と表現する人がいたら、やっぱりヘンです。「私の国」を「私の故郷」という意味でなく、「日本」という意味で言うとしたら、「青年の主張」かなんかで、親父が右翼団体かなんかやっているような、たいがい処女の女子高生が使うくらいではないでしょうか。 従って、ここは「私」と「我々」の境界が曖昧な日本語の特性によるところもあって、それ自体、意味があるのでしょうけど、「我が国」は「OUR COUNTRY」に近い言葉とすべきであり、これを「MY COUNTRY」と訳したことにミスがあったということになります。それにしても一会社員、一大学教員、一公務員が「我が国」と、こうも頻繁に表現するのはヘンというわけです。 「私」の範囲、「私」と「私たち」の境界、「私」と「公」の境界とともに、「国」という観念の違いでもあって、幾度も指摘されながら、今も「日本語」ではなく「国語」と呼ぶことにも、この国の特異性があります。日本史を「国史」と読んだ時代の遺産が今もここには残っているわけですけど、単に国粋的、右翼的ということの問題ではなく、ここは自分と国と世界をどう頭の中で位置づけているのかという問題なのでしょう、たぶん。 かく言う私も「我が国」と書くことはありますが、通常の文章では「日本」だったり、「この国」という言い方をしています。ちょっとお堅いことを書かなければと思うと、「我が国」なんて書いてしまうんですね。それにしたって、「我が国」と書けてしまう私もまた日本人的な言語感覚を間違いなくもっていて、日本人的な心象をもっているのでしょう。 面白いですよね、こういう言葉遣いの話は。 * 時には「我が国」と表現してしまう私であっても、誰に言われることもなく、「うちの会社」という表現が昔から大嫌いでして、サラリーマン時代もこういう表現をしたことがありません。社長や創設者がこういうのは理解しますよ。「うちもずいぶん売上が伸びたものだ」「うちの社員は使えないのが多い」なんて、会社や社員を個人の所有物としているみたいですけど、現に社を代表し、会社を作ってきたと自覚していい人が言うのですから、違和感がさほどありません。しかし、一社員が「うちの会社」というと、「バカか。安い給料でこき使われているだけなのに、いつからおめえの会社になったんだ」と内心思います。 私個人で言えば、「うち」と言えるのはほぼ「家族」だけです。「うちの家族」「うちの親」という言い方までは私もしていると思います。「うちの家族」と言ったって、遠く離れて住んでいる親と姉のことですから、あんましこういう言い方もしないと思いますけど、結婚していたら、「うちの家内」とか「うちのヤツ」って言うのかもしれませんね、私も。いや、冗談以外では、言わないか、やっぱり。 恋人という存在にも、「オレの彼女」「オレの女」とかって表現することにためらいがあります。前に「黒子の部屋」に書いたように、「つきあっている」という言葉にも疑問のある私ですけど、言うとしたら、「つきあっている彼女」とかって言うでしょう。 「うちの妻たち」って風俗妻を表現していることは何度かあったと思いますけど、これは、風俗嬢と客という関係のまま婚姻関係が成立していると考える「風俗妻プロジェクト」(最近、「黒子の部屋」を読み出した人は知らないでしょうけど、家族制度を相対化するため、こういう壮大な実験をやっているのです)の一環であり、あえて風俗嬢を風俗嬢という立場のままで家族内に引き込む意図のためです。 家族であれば「うち」と言っていいのと同じく、十人に満たないような会社であれば、構成員全員の人となりがわかっていて、同じ釜のメシを食っているとの感覚も強まりますから、「うち」と表現することにもさほどの違和感がありません。風俗店の従業員が「うちのコたち」というのも違和感がないです。でも、一部上場企業の末端社員が「うちの」と言うと、「おめえんちは、一体何百人家族がいるんだよ」と言いたくなってしまうのです。 たぶん、こういう言葉を使えるというのは、個の自立みたいなことにも関わってくるんだと思うのですが、把握もできないくらいに大きな組織を「うち」と言ってしまえるのは、日本の会社が疑似家族として成立しているということだけでなく、あるいはそれとも関わって、自己と集団を同化してしまえる、自己と他者の境界を曖昧にしてしまえるということでもあって、高木氏が言うように、このことは公益性を認識できないことにもつながっていきます。 一見、この「番外」とは何ら関係のないような話をしてしまいましたが、ここからさらに話は続いていきます。 |
| ←真実・篠田博之の部屋topへもどる | page top ↑ |