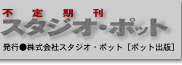 |
| ▲ゴト技top| 第15章 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9| 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18| 19| 20| 21| 22| 23| 24| 25| 26| 27| |
| [第15章●その他よしなしごと] 10… わたしの進化観 |
[2005.02.24登録] |
| 石田豊 |
前に個人サイトの方に書いたことと重複するし、またここでのテーマからもいささか逸脱するかもしれないけれど、先日来うすぼんやり考えていることを書いてみる。 「生きた化石」という言葉がある。たとえばカブトガニとかに対して冠せられる形容だ。太古の姿のまま、現在も生きているという意味である。シーラカンスはまさにこれだし、時としてゴキブリなんかもこう呼ばれたりする。 この言い方にはプラスのイメージはない。生きた化石だからエラいと思っているわけじゃない。どちらかといえば、古くさいまま長らえている劣ったヤツというニュアンスだ。 今も十分現役で生きているということは、とりもなおさず、「今でも通用している」ということである。ゴキブリなんぞにいたっては、通用しているどころか、きわめて繁栄しているように見える。古いデザインのまま、長年にわたって通用するということは、取りも直さず基本設計の優秀さを物語るものだ。ゴキブリやカブトガニやシーラカンスは、古くさく劣っているわけではなく、とてつもなく長い年月、現役として通用するだけの力を持った優れたヤツらであるのだ。そこまで持ち上げなくても、とてつもなく運がよかった連中とくらいは言ってやることができる。 進化論の始祖であるダーウィンは1809年生まれ。19世紀人である。その時代性もあるのだろうが、進化論は近代社会のイデオロギ−に色濃く彩られている。「社会進化論」なんてふうに使えばなおさらだ。進化=善という前提。 しかし、進化ということをまともに考えれば、進化はいいことだというような結論は出てこない。進化というのは「生」の問題ではなく無数の「死」の結果であるからだ。 「フィンチの嘴」という魅力的な本がある。ガラパゴス諸島で20年にわたってフィンチと言う小鳥を個体識別するという徹底的な方法で研究した結果を中心にレポートしたものだ。いままでなかなか目に見えなかった「進化」が、ここでは経年的な計測結果の数字で実証できるという。 長く続いた旱魃のあと、ある種のフィンチの嘴は大きくなった。旱魃の中では柔らかい実をつける植物がすべて枯れてしまい、彼らの餌である種子は、固く大きなものだけしかなくなった。固く大きな種子を食べるためには大きな嘴がいる。 つまり、フィンチは旱魃という環境の中で、それに適合するように「進化」したわけだ。 このプロセスはいかにして達成されたか。それはなにも新しく生まれるヒナたちの嘴が大きくなったわけではなく、より小さな嘴をもつ鳥たちが死に絶えたからに他ならない。変化は「嘴の大きな鳥が増える」ことで起こったわけではなく、嘴の小さな鳥がすべて死に絶えることで実現した。 つまり、進化とは勝者の生の物語ではなく、勝者の生が変化の原因につながらない以上、敗者の無数の死の物語なのである。 進化するということは、いってみれば哀しい物語なのだ。進化しないですむなら、そっちの方が(多くの個体とその遺伝子にとって)大いに幸せである。 この見方に気がついた時、進化というものがストンとわかったような気がしたと同時に、なんだかとても悲しい気持ちもした。それ以来たとえば「アプリケーションがいっそう進化し、○○が○○できるようになった」なんていう表現が書きづらくなっている。 ま。アプリケーション制作の現場でも、無数の失敗の結果としての完成品があるわけではあるのだが。 |
この記事は
|
お読みになっての印象を5段階評価のボタンを選び「投票」ボタンをクリックしてください。 |
投票の集計 |
投票[ 5 ]人、平均面白度[ 4.2 ] ※「投票」は24時間以内に反映されます※ |
ご意見をお聞かせください |
|
| ←デジタル/シゴト/技術topへもどる | page top ↑ |
| ▲ゴト技top| 第15章 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9| 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18| 19| 20| 21| 22| 23| 24| 25| 26| 27| |

