佐々木敦『ニッポンの思想』
佐々木敦氏のことは四半世紀以上前から知っている。知っているといってもお目にかかったこともなければ、メールのやり取りをしたこともない。ただ、大学時代に、伏見の幼なじみが佐々木氏と早稲田で友人になって、「佐々木という面白いやつがいる」とやたら語っていたので間接的に知っていた(たぶん、頻繁にその名前が会話のなかに出ていたので記憶しているのだと思う。きっと彼は四半世紀前から異彩を放っていたのだろう)。そして、ある時期からたまにメディアでその名前を目にして、たぶん、あのときの「佐々木」がこの人なんだろうなあとは思っていたけれど、文章を読んだりすることもなく、この本で初めて彼の言葉に触れた。
感想は、同世代で思想やカルチャーに関心を持って勉強していたインテリなら、きっとこういうラインで思想状況を捉えるのだろうなあというもの。伏見みたいに浅田彰氏の『構造と力』を最近まで『構造と刀』だと思っていた手合いにとっては(←バカ)、ポスト構造主義なんていうのは、自分がセクシュアリティの問題を考えていく果てに出てきたもので、思想を思想として興味など持つこともなかった。だから、この本の流れも、思想を思想として興味を持てる人にとっての趣味趣向が濃厚に反映されていると思った。言葉は悪いが、思想マニアがどのあたりをイキどころにしてきたのかという。伏見は目的論的にしか思想を理解する力がないので、結局、ここで語られた思想の内実はあまりわからなかったが、80年代以降の「ニッポンの思想マニア」というのなら、たしかに、イメージできた。

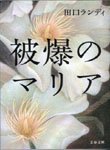 伏見は共同だったか時事だったかで単行本版の書評を書いたのだが、それが著者の目にとまったらしく、文庫版の解説を書かせてもらうことになった。よい機会だったので田口ランディ氏の他の作品も読み返してみたら、どれも彼女しかアクセスできないような異界を抱えていて、その異空間にからだごと呑み込まれそうになった。恐ろしい魔力を持った作品を指先から滴らせる人だと思った。
伏見は共同だったか時事だったかで単行本版の書評を書いたのだが、それが著者の目にとまったらしく、文庫版の解説を書かせてもらうことになった。よい機会だったので田口ランディ氏の他の作品も読み返してみたら、どれも彼女しかアクセスできないような異界を抱えていて、その異空間にからだごと呑み込まれそうになった。恐ろしい魔力を持った作品を指先から滴らせる人だと思った。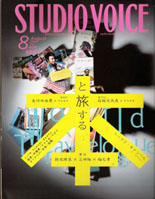 「STUDIO VOICE」といえばバブルの時代にはオシャレの代名詞のような雑誌だった。伏見はこれまで書評を上げてもらったくらいの関係しかなかったのだけれど、そこからコラムの依頼をいただいてとても光栄に思った。そして「今後ともよろしく」と原稿を送ったら、なんと、次号で休刊が決まったという! 部数と広告の減少が止まらず会社を解散するとのこと。なんとも寂しいが、そういう時代なんだなあと溜め息が出た。
「STUDIO VOICE」といえばバブルの時代にはオシャレの代名詞のような雑誌だった。伏見はこれまで書評を上げてもらったくらいの関係しかなかったのだけれど、そこからコラムの依頼をいただいてとても光栄に思った。そして「今後ともよろしく」と原稿を送ったら、なんと、次号で休刊が決まったという! 部数と広告の減少が止まらず会社を解散するとのこと。なんとも寂しいが、そういう時代なんだなあと溜め息が出た。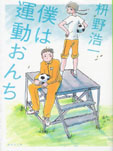 最近、よくエフメゾにおみえになる枡野浩一さんから新刊をいただいた。お店では「サイコ」「ストーカー」あつかいされている枡野先生であるが(笑)、これはとてもさわやかな青春小説。主人公は運動も勉強もできない男子高校生で(でもチンコはでかい)、彼の友情や恋をちょっと笑えてちょっと切なく描いている。
最近、よくエフメゾにおみえになる枡野浩一さんから新刊をいただいた。お店では「サイコ」「ストーカー」あつかいされている枡野先生であるが(笑)、これはとてもさわやかな青春小説。主人公は運動も勉強もできない男子高校生で(でもチンコはでかい)、彼の友情や恋をちょっと笑えてちょっと切なく描いている。