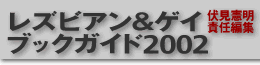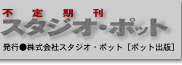|
十数年前、『プライベート・ゲイ・ライフ』(学陽文庫、『ゲイという[経験]』収録)を執筆している頃の私には、「ゲイ」「ホモ」「同性愛者」といったカテゴリーは、自分を抑圧し差別するような被差別記号でしかありえなかった。というか、まだ余裕がなくて、そうしたネガティブな側面にしか思考が向いてなかった。それに、80年代には思想オンチでポストモダンにはとんと関心のなかった私も、気分としてはポスト構造主義的なるものに影響を受けていたのだろう。なんとなく、「同一性」とか「共同性」といったものに対する否定的な感覚は共有していた。だから私はその処女作に、これはゲイ解放宣言の書であるとともに、「しかしいずれは「ゲイ」というカテゴリーが解体されるのが『正しいこと』だ」というふうな主旨を、はっきりと記していた。そういう意味では、すでに、90年代半ばに欧米から輸入されることとなったクィア・セオリーとも方向性を共にしていたのだろう。
そうした感受性は、同時期に発表されたレズビアン・スタディーズの嚆矢、掛札悠子『レズビアンである、ということ』(河出書房新社)にも見出される。そこでもすでにレズビアンという主体の構築性と、それへの懐疑が問題意識としてはっきりと打ち出されていた。
日本における同性愛差別の政治構造を明らかにしようとした最初の仕事としては、平野広朗の『アンチ・ヘテロセクシズム』(パンドラ、1994)が挙げられるが、それに続くゲイ・スタディーズとして上梓されたまさに『ゲイ・スタディーズ』(青土社、1997)は、日本のゲイ「解放運動」を担ってきた動くゲイとレズビアンの会の、キース・ヴィンセント、風間孝、河口和也によって著された。けれども、この本の理路も、政治的な主体としては「同性愛者」を立てて戦略的にそれを使っていかざるをえないとするが、「同性愛者」という主体自体は政治的な意匠として以外には重視されない。
これらはどれも、差別と抑圧の根源は「同性愛者」のカテゴリー化により生じたものあり、そうした土俵自体を解体しないでは差別と抑圧は解消されない、とするロジックを内に持っている。それは、現在ジェンダー・スタディーズを席捲している社会構築主義、クィア・セオリーとも同様のものである(この手の議論の入門書としてはアエラムック『ジェンダーがわかる。』(朝日新聞社、2002)がわかりやすい)。つまり、日本のレズビアン&ゲイ・スタディーズは、最初から、単純な本質主義からは始まっていなかったのだ。しかしその理路においては、ジュディス・バトラー『ジェンダー・トラブル』(青土社、1999)に代表されるクィア・セオリーと言われるものほどの徹底さはなかった。つまり、政治的な戦略としてはともかく、理論としては中途半端なものだったと言えるかもしれない。
そのようにレズビアン&ゲイ・スタディーズの議論の流れを喝破したのは、伏見憲明編『クィア・ジャパンvol.3 魅惑のブス』(勁草書房)に「クィア理論とポスト構造主義」という論文を発表した野口勝三である。そして野口は返す刀で、実はそういうクィア・セオリー自体も、真理主義の罠に陥っていると、批判する。土俵を解体することが正しい、とするのは、ひとつの形而上学的(=否定神学)な観点だ、クィア・セオリーの理路は、人々の実存の中から生じたものではなく、思弁的な理念にすぎないというのが、彼の議論である。
ポスト構造主義の思想それ自体を批判の射程に入れた野口勝三の理論は、近刊『正義』(ポット出版、2002)でも展開される。今後、ジェンダー/セクシュアリティの領域で、そうした新しい思潮が台風の目となることは間違いない。
●もくじ・はじめに
●ゲイ&レズビアン・ライフ
●セクシュアル・マイノリティ
●同性愛の歴史
●クィア・カルチャー
|