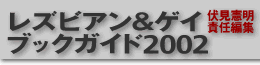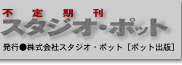|
共同体の鎹(かすがい)となるのが「歴史」というものならば、コミュニティというフィクションをより豊かなテーマパークとするために、過去の事実を「歴史」として再構成してみるのも意味のあることかもしれない。「歴史」はアトラクションだ。
私は最新刊『ゲイという[経験]』(ポット出版、2002)の「ゲイの考古学」という章で、男性同性愛者の前近代から戦後までの「歴史」を、「欲望の自己実現」という視点から素描する試みをしている。ミシェル・フーコーの『性の歴史』(新潮社、1986)以後の、同性愛者という主体は近代に構築された云々…の方程式に単純に乗っかるのではなく(最近のアカデミズム系はその手の安直な仕事が多くて、ウザい)、もう少し当事者の欲望に添った形で同性愛の時間の流れをたどってみようと思った。ハッテン場やゲイバーの歴史からゲイ媒体の源流まで、文献ばかりでなく、足をつかって調べ上げているので、ぜひともご一読いただきたい。
また学術論文としては、上野千鶴子編『岩波講座現代社会学10 セクシュアリティの社会学』(岩波書店、1996)などに収録されている古川誠の論文が、信頼度の高い研究となっている。同性愛の歴史を探訪しようとする者には必読であろう。
海外のゲイの「歴史」を概観したいという人に一番お勧めなのは、サイモン・ルベイ『クィア・サイエンス』(勁草書房、2002)。この本は基本的には生物学的な学説において同性愛がどのように語られ、その「原因」がどの程度明らかになっているのかを論述した科学書なのだが、同性愛をめぐる学説の変遷を通じてゲイの「歴史」自体が理解できる内容になっている。そういう意味で、かなり役に立つ教養書だ。
西洋のレズビアンの「歴史」が知りたければ、リリアン・フェダマン『レスビアンの歴史』(筑摩書房、1996)という労作が翻訳されているので、こちらを参照するのがいいだろう。日本のレズビアンについては、まだまとまった仕事というのは現われていないが、研究者の中にそうしたテーマを選択している人もいるようなので、いずれ読むことができるかもしれない(あるいは、貴方自身が執筆してみてもよい!)。
日本の近代以前の男色などに興味を持つのなら、つい最近、男色研究の草分け、岩田準一(故人)の代表作『本朝男色考 男色文献書誌』(原書房、2002)が復刊されたので、それを紐解くのがいい。同性愛に関心を持つものならば、一度は目を通しておきたい古典中の古典である。
もはや「歴史」となってしまった70年代アメリカのゲイ・リベレーションの象徴、ハーヴェイ・ミルクの生涯をルポルタージュしたランディ・シルツ『ゲイの市長と呼ばれた男』(草思社、1995)や、アメリカでのエイズ渦の過程を探った同『そしてエイズは蔓延した』(草思社、1991)は、ノンフィクション作品として一級の面白さなので、必ずしも同性愛に関心のない読者にも十分に訴えるだろう。
また、「歴史」という意味だけでなく、エドマンド・ホワイト『アメリカのゲイ社会を行く』(勁草書房、1996)、『燃える図書館』(河出書房新社、2000)、栗木千恵子『アメリカのゲイたち』(中央公論社、1998)などを読むと、アメリカと日本では同性愛に対する社会の基盤となるものが相当に異なることが理解できる。それは単純にどちらが同性愛に寛容かというような話ではなく、その抑圧の構造がキリスト教のような「原理」によっているのか、「世間」というような相関関係、雰囲気によっているか、という違いだ。そして、後者の方が柔構造であるという点で、私たちジャパニーズ・レズビアン&ゲイは今、かなり「面白い」状況の中に置かれている、と言える。そうした問題については、『クィア・ジャパンvol.2 変態するサラリーマン』(勁草書房、2000)のインタビューで、宮台真司が論及している。欧米中心主義の視点から日本を遅れていると一方的に裁断するのではなく(日本という状況と格闘していない日本人にこそ、よく見られる主張なのだが)、表層的には捉えづらい差別の内実を冷静に分析することで、日本のゲイ&レズビアン・ムーブメントの方向性がはっきりと見えてくるだろう。
そのためにもそれぞれの「歴史」を深く検討してみる必要があると痛感する。
●もくじ・はじめに
●ゲイ&レズビアン・ライフ
●セクシュアル・マイノリティ
●クィア・カルチャー
●レズビアン&ゲイ・スタディーズ
|