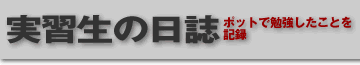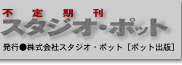|
�@���̖{�̂܂Ƃ߂͓����Ő���ɓn���čs���܂������A�\�L��t�H�[�}�b�g�����ꂳ��Ă��܂��A�Ȃɂ����A������₷���܂Ƃ߂���Ă��Ȃ��̂ŁA�����ɓƗ��R���e���c�Ƃ��āA�ȑO�܂Ƃ߂����̂�⑫�E�������Ȃ���A�������A�����Ɏc���Ă������Ǝv���܂��B
�@�����ǂނ��ƂŁA���̖{�ɏ�����Ă���A�v�_�A�����Ŕ��f�������̂ł͂���܂����A�����ł��m�F�ł���悤�ɂ��Ă����A�Ƃ������Ƃ��o����悤�܂Ƃ߂Ă��������Ǝv���܂��B
�@�܂��́A���̖{�̍\�����A�������������āA�����Ă������Ǝv���܂��B����ɉ����Ă܂Ƃ߂Ă����̂ŁA�Q�Ƃ��A���Ă�����Ε�����₷�����Ǝv���܂��B
���\�\�\�\�\�\�\������(�܂Ƃ߂��Ƃ��낾���s�b�N�A�b�v)�\�\�\�\�\�\�\��
��1��
�����͂͊������܂�
��2�́@�{���ǎ҂ɓ͂��܂Ł\�o�ŗ��ʂ̂����݁\�c�c�c�c�o13
�@1.�o�ŋƊE�Ƃ́c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�o13
�@2.�o�ŗ��ʂ̃��[�g�ɂ��āc�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�o15
�@3.�o�Ŏ҂ɂ��āc�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�o17
�@4.�̔���Ёi�掟�j�ɂ��āc�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�o18
�@5.���X�ɂ��āc�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�o21
�@6.�m���Ă��������ƊE�c�́E�g�D�Ȃǁc�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�o25
��3�́@�o�ŋƊE���x�����̐��x�ɂ��āc�c�c�c�c�c�o28
�@1,�Ĕ̔����i�ێ����x�i�Ĕ̐��x�j�Ƃ́c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�o28
�@2.TONETS����SUPERTONETS�ւ̓W�J�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�o31
��2��
��1�́@���Ђ̕��ނɂ��āc�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�o37
�@1.���e�̕��ނ̎d���c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�o37
�@2.�̔��Ώۂɂ�镪�ނ̂������c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�o44
�@3.���s�`�Ԃɂ�镪�ނ̂������c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�o45
��2�́@���Ђ̗��ʏ����ɂ����c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�o47
�@1.�ϑ����x�Ƃ́c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�o47
�@2.�����萧�x�̂��āc�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�o50
��3�́@�������x�ɂ��āc�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�o52
�@1,�����̂����݁c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�o52
�@2.�����i�Ƃ́c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�o52
�@3.�����[�̎�ނƖ����c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�o52
�@4.�����̗���c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�o55
��4�́@������s���ƒ�������c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�o56
�@1.������s���Ƃ́c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�o56
�@2.��������c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�o56
���\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\��
����2�́@�{���ǎ҂ɓ͂��܂Ł\�o�ŗ��ʂ̂�����
�i�P�j�o�ŋƊE�Ƃ́iP13�j
�@�o�ŎЁE�掟�E���X�����ďo�ŋƊE3�҂ƌĂт܂��B����3�҂ɍi���ďo�ŋƊE�̊W���܂Ƃ߂�ƁA�o�ŎЂɂ���Ė{�����삳��A�掟�Ǝ҂ɂ���ď��X�ɕ��z����A���X�ɂ���ēǎ҂ɔ̔������A�Ɓ\��܂��ł����i�{���Ɂj�\�Ȃ�܂��B����3�҂��X�ɂ܂Ƃ߂Ă����܂��B
�i2�j�o�ŎЂɂ��āiP17)
�@�o�ŎЂ͖{�̊����l���A�������ɓ��e�E���ҁE�����E�̍فE���ʁE�艿�E���s�����E���s�����Ȃǂ����߁A���̈�A�Ɍ������d�˂Ă����܂��B�܂��A�o�łƂ����̂́A�o�ŎЂ����ōs������̂ł͂Ȃ��A�Ⴆ�Έ���ƎҁE���{�ƎҁE�ۊNjƎҁi�ɂ̕ۊǏꏊ�j�ȂǗl�X�ȋƎ҂Ɗւ���Ă��܂��B�iP�W�j
�@���{�̏o�ŎЂ̑����́A4302�ЂŁA���̂��������ɂ���̂�3607�ЂƖ{���ɂ͏�����Ă��܂��B���̂��ߗ��ʂ͓������N�_�ɑS���֗���Ă��܂��B�����A�o�ŋƊE�ɂ́A�ϑ����x�i�̂��ɂ܂Ƃ߂܂��j�����邽�߂ɏ��X����̕ԕi������A���ʂ͈���ʍs�ł͂���܂���B
�i3�j�̔���Ђɂ��āi�P�W�j
�@���[�J�[�ł���o�ŎЂƔ̔��@�ւł��鏑�X�̒��ԂɈʒu���A�o�ŎЂɑ���o�ŕ������X�֔̔����A�����X�ɑ���o�ŎЂ��o�ŕ����d����A�o�ŕ���S���I�ɃX���[�Y�ɗ��ʂ�����̂��掟�ł��B
�掟����̂悤�ɗ��ʂɂ�����������ʂ������߂̋@�\�����ɂ܂Ƃ߂܂��B
�E���X�ւ̏��i���z�E�������f�[�^�ɂ��Z�o���e�X�̓����ɍ��킹���z�{
�E�G���E������s���E�S�W�Ȃǂ����X�̊�]�����ɉ����Ċm�ۂ��z�{
�E�S���̏��X����A�����������A�ꊇ���ďo�ŎЂ֎x�����B
�E���i�̕��ށE�����E�d�����E����E�o��
�E���i�̃X�g�b�N
�E�e��f�[�^�̒����E�W�v�E���́E��
�E���̑�
�@�掟�ɂ́A�o�ŎЂƏ��X���S��˂Ȃ�Ȃ����S���y�����邾���ł͂Ȃ��A���~���ȗ��ʂ̂��߂̋@�\����������悤�Ɏv���܂��B
�i4�j���X�ɂ��āiP21�j
�@�o�ŕ��y�т���Ɋւ�����̂��A�o�ŎЁE�掟���璲�B���A����҂ɔ̔�����̂����X�ł��B
�����ōŋ߁i�{�����s��������5�N���j�̏��X�̌`�Ԃɂ��Ă܂Ƃ߂܂��B
��^��
�@�ǎ҂����Зނ��w������ہA�������╶�ɂȂǂ͋ߗ��X�ŁA��发��P�s�{�Ȃǂ͕i��̑����s�S�^�[�~�i���̑�^�X�ōw������X���������܂��B�ǎ҂́A���̏��i�\���̖L��������A������T���y���݂̂����^���X�ɑ����^�Ԃ��Ƃ������悤�ł��B
������
�@�ǎ҂̃j�[�Y��C�t�X�^�C���ɍ��킹�ď��X�̂�������ς���Ă��Ă��܂��B���X�ł��o�ŕ������łȂ��AAV�E�J�Z�b�g�u�b�N�E�t�@���V�[�O�b�Y�E�e���z���J�[�h�̔̔��A����ɂ̓r�f�I�ECD�����^�����ڗ����Ă��Ă��܂��B
��剻
�@�������ɑ��Ă�����̕����Ƃ��Đ�剻������܂��B�戵���i�̍i���݁E����W�������Ɋւ��\�Ȍ��葵����A�Ƃ������悤�ȏ��i�\�����s�����X�������Ă��Ă��܂��B����́A�q�w���͂��s���ו������Ď��X�ɍ������i����������Ƃ������̂ł����A��ɂ܂Ƃ߂�u��4�͏o�ŗ��ʃl�b�g���[�N�v�ɂ�����A�o�ŋƊE3�҂ɂ�������`�B�̉\���A���̂悤�ȌX���̈���ɂȂ��Ă��邩������܂���B
�i5�j�o�ŗ��ʃ��[�g�ɂ��āi�o15�j
�@�o�ŎЂ���ǎ҂ɏo�ŕ����n��ߒ��͗l�X�ł����A�����Ƃ��������p����郋�[�g�Ƃ��āA���탋�[�g�ƌĂ����̂�����܂��B���Ɏ����Ă����܂��B
�o�ŎЁ\���̔���Ё\�����X�\���ǎ�
�@���̃��[�g���ꕔ�����Ă����܂��B
�@�o�ŎЁE�掟��ʂ��A���X�ɑ��肻�̑������X�i�w�������E�L���X�N�ECVS�Ȃǁj�Ŕ̔�����郋�[�g�A�̔���Ђ͒ʂ����ɏ��X�₻�̑������X�ɒ��ڏ��i���������[�g�A�܂��o�ŎЂ��璼�ړǎ҂ɔ̔�����郋�[�g������܂��B
�i6�j�m���Ă��������ƊE�c�́E�g�D�Ȃǁi�o25�j
�@���{���Џo�ŋ���F����А��S�X�O
�@���{�G������@�@�F����А��V�S
�@���{�o�Ŏ掟����F����А��S�Q
�@���{���X���Ƒg���A����F������X���P�Q�O�P�V�@�@
����3�́@�o�ŋƊE���x�����̐��x�ɂ��āi�o28�j
1.�Ĕ̔����i�ێ����x�i�Ĕ̐��x�j�Ƃ�
�i1�j�Ĕ̐��x�Ƃ�
�@���[�J�[�ł���o�ŎЂ��A���Џ��i�̔̔����i�����߂āA�����̔���Ђ⏑�X�Ȃǂ̔̔���Ɏ�点��Ƃ������̂ł��B
�@���̌_��́A�o�ŎЁ\�̔���ЁA�̔���Ё\���X�ԂɌ��Ԃ��̂ł��B
�@
�i2�j�Ĕ̐��x�̕��݁i�o28�j
�@���a28�N�ɓƐ�֎~�@�̈ꕔ����������邱�Ƃɂ���āA�Ĕ̐��x�͔������܂����B���̌㏺�a53�N�Ɍ�������ψ�����o�ŕ��̍Ĕ̐��x�p�~�̈ӌ���\�����܂���
�@��������ψ���̈ӌ��͉��̂悤�Ȃ��̂ł��B
�@�o�ŋƊE�ɍĔ̉^�p�̍s���߂�������A�艿�̔����`���ƍl�����d�������Ă���B����͗��ʉߒ��ɖ�肪����A�s���Ȏ�����ʂ������Ă���̂ł͂Ȃ����A�����Ă��͂�o�ŕ��͕������ł͂Ȃ�������I�X���������A�@���ŕی삷��K�v�͂Ȃ��B
�@�Ƃ����悤�Ȃ��̂ł��B������_�@�ɏ��a55�N�A�V�������x�����{����邱�ƂɂȂ�܂����B�ȉ��̒ʂ�ł��B
1.�Ĕ̂��̗p���邩�ۂ��͏o�ŎЂ̎��R�ӎu�B������Ĕ̂Ƃ����܂��B
2.�Ĕ̏��i�Ƃ�����̂ɂ́A�u�艿�v�̕������o�ŕ����̂ɕ\�����邱�Ƃɂȁ@��܂��B
3.��x�Ĕ̏��i�Ƃ��ďo�ł������̂ł��A�����Ԍ�ɑS�Ă̏��i���������ŁA�o�ŎЎ��炪�u�艿�v�̕\�������邱�Ƃ��ł��܂��B���������̂��Ƃ͔̔���Ђɒʒm���Ȃ��Ă͂Ȃ�܂���B����������Ĕ̂Ƃ����܂��B
2.�ϑ����x�ɂ����i�o31�j
�@�u�Ĕ̐��x�v�Ɓu�ϑ����x�v���o�ŋƊE�̓������Ƃ��ċ�������2�̐��x�ł��B�Ĕ̐��x�ɂ��Ă͊��ɂ܂Ƃ߂��̂ŁA�����ł͈ϑ����x�ɂ��Ă܂Ƃ߂܂��B
�@���ԓ��ł���A�ԕi���邱�Ƃ��ł���A�Ƃ����_����o�ŎЁ\�̔���ЁA�̔���Ё\���X�Ō��Ԑ��x�̂��Ƃł��B
�E�ϑ����x�̗��_
�@���X�����댯�̕��S���y���ł���B�܂�A���X���������{���A�S�Ĕ���K�v�͂Ȃ��A�Ƃ������Ƃɂ��A���X�ɑ���ށA���ʂ̖{������邱�Ƃ𑣂��B
�E�ϑ����x�̖��_
�@�o�ŕ��̐��Y�ߏ�A�⏑�X�̔̔��\�͂��������Ȃǂ̗��R�ɂ��A�ԕi��K�v�ȏ�ɑ��������Ă��܂��A�Ƃ������ƁB
����4�́@�o�ŏ��l�b�g���[�N�ɂ����i�o32�j
�@�����ł́A���x��Љ�ɂ�����o�ŋƊE�̏����̓W�]�ƁA���̋�̓I�Ɏ��{����Ă���V�X�e���ɂ��Ă܂Ƃ߂܂��B
1.���x��Љ�̐i�W�Əo�ŋƊE�̏���
�@�R���s���[�^�[�����p�������l�b�g���[�N�̕��y�ɔ����A�f�[�^�ʐM���o�ꂵ�A�R���s���[�^�[���S�̃l�b�g���[�N�V�X�e�����\�z���ꍂ�x��Љ�̐i���A���W�ɍ��킹�A�o�ŗ��ʂ��ς���Ă��Ă���B
�@�����̔��W�́A�o�ŎЁA�̔���ЁA���X�Ԃ��l�b�g���[�N�Ō��т��邱�ƂɂŁA�o�ŗ��ʂ̏�̑��i�ɑ傫���v�����Ă��܂����B
�@�����āA�����I�ɂ͂��̎O�҂𑍍�����l�b�g���[�N���\�z����o�ŋƊE�̔��W�͂܂��܂��i��ł����Ǝv���܂��B
�ESUPER TONETS�ɂ���
�@SUPERTONETS�Ƃ́A�o�ŎЁA�̔���ЁA���X�Ԃ����ԃl�b�g���[�N�V�X�e���ł��B
�@���X�ɂƂ��ẮA�Ɩ��ʁA�@�\�ʁA�̃V�X�e���I�����\�ɂȂ�A�e���X�ɂ����������I�ȃV�X�e���������ł���悤�ɂȂ�܂��B
�@�o�ŎЂɂƂ��ẮA�[�i�A�ԕi�A���l�X�Ȕ���グ���т��͂��߁A���|�����A�ɁA��łȂǂ̊e����̊Ǘ��̌�������}�邱�Ƃ��ł���悤�ł��B
��2���@���Ђɂ����i�o35�j
�@�����܂ł́A�o��3�҂ɂ����闬�ʂƁA���̊ԂŌ���鐧�x�ɂ��Ă܂Ƃ߂܂����B��������́A���Ђɂ��āA���ޕ��@�̂������̗�A���̃����b�g�A����Ə��Ђ̗��ʏ����Ȃǂɏd�_��u���Ă܂Ƃ߂Ă��������Ƃ������܂��B
����1�͏��Ђ̕��ނɂ����i�o37�j
�@���Ђ̕��ނ́A���̖ړI�ɂ��A�l�X�ȕ�����������Ă��܂��B���e�ł̕��ށA�̔��Ώۂɂ�镪�ށA���s�`�Ԃɂ�镪�ނȂǁA�l�X�ȕ��@�ł̕��ޖ@�̂��������܂Ƃ߂����Ǝv���܂��B
1.���e�ɂ�镪�ނ̂������i�o37�j
�i1�j���{�\�i���ޖ@�iNDC)
�@���{�̐}���قɓK�����A�W�����ޖ@�Ƃ���Ă��܂��B���̕��ޖ@�ł����A�u�ށv�u�ԁv�u�ځv��3�i�K�������ĕ����Ă��܂��B
�E�u�ށv�Ƃ�
�@�����镪����A�N�w�A���j�A�Љ�Ȋw�A���R�Ȋw�A�H�w�A�Y�ƁA�|�p�A��w�A���w�A����ƁA�����ɑ����Ȃ����̂��A���L�A�Ƃ��āA�S����10����ɕ����Ă��܂��B���̋敪���ނł��B
�E �u�ԁv�Ƃ�
�@���ꂼ��́u�ށv�Ɋւ��A����ɏڂ������e��10�ɋ�ʂ������̂��u�ԁv�ł��B
�E�u�ځv�Ƃ�
�@����Ɋւ��Ẳ�����{���ł͂���Ă��Ȃ��̂ŁA�u�ځv�A�Ƃ́A�u�ԁv������ɏڍׂɕ��ނ���̂��Ǝv���܂��B
�i2�j���{�}���R�[�h�ɂ�镪�ނ̂�����
�@�uISBN�R�[�h�v�Ɂu���ރR�[�h�v�A�u���i�R�[�h�v��2�������ĕ\������R�[�h�̌n�������܂��B
�EISBN�R�[�h�Ƃ�
�@���ەW���}���ԍ��ƌ����A���Ƃ������́A���Ƃ����o�Ŏ҂́A���Ƃ����^�C�g���̏o�ŕ���\���̂��A����肷�邱�Ƃ��o���܂��B�����Ă�����A��P�`��4������4�ŕ\�����܂��B
�@�@��P�����F���ʋL���B���̍��Ƃ́A����ʂɕ�����ꂽ���ł��B���Ȃ�
�@�@�@�@�@�@�@�Ɂu4�v�͓��{��\���܂��B
�@�@��2�����F�o�ŎҋL���B
�@�@��3�����F�����ԍ��B�X�̏o�ŕ��̌ŗL�ԍ��̂��Ƃł��B
�@�@��4�����F�`�F�b�N�����B�R���s���[�^�[�������I�ɔ��f���邽�߂̐����@�@�@�@�@�@�@�ł��B
�@
�E���ރR�[�h�Ƃ�
�@�o�ŎҁA�̔���ЁA���X�A�}���قȂǂŁA���ނ⏤�i�Ǘ��̕ւ�}�邽�߂ɓ������ꂽ�R�[�h�̌n�ł��B
�@���̕��ޖ@�́A�u�̔��ΏۃR�[�h�v�A�u���s�`�ԃR�[�h�v�A�u���e�R�[�h�v�̂R�̋敪��萬�藧���Ă���悤�ł��B�����3�͌���X�ɂ܂Ƃ߂܂����A���{�\�i���ޖ@�Ƃ͈�������_���番�ނł��Ă���悤�ł��B
�@���āA���{�}���R�[�h�́A���2�ƁA���i�R�[�h���琬�藧���Ă��܂��B��̓I�ɋ����Ă݂�ƁA
�@ISBN4-7631-8959-X �@C0030�@ P1030E
�@|�@ ISBN�R�[�h�@�@ �@|�@ |���ށ@|�@|���i�R�[�h|
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �R�[�h
�@�Ƃ����悤�Ȋ����ɂȂ�܂��B�{���ɍڂ��Ă������̂����̂܂ʂ��܂����B���i�R�[�h�̉�����ڂ��Ă��Ȃ��̂ł����A�ǂ�Ŏ��̔@���A���i���������̂ł���Ǝv���܂��B
�@�i1�j�ł܂Ƃ߂��A���{�\�i���ޖ@�Ƃ͈Ⴂ�A�o�ŕ��̓��e�ȊO�����ނ̗v���Ɋ܂ނƌ����_�ŁA���ʂƂ����ړI�����m�ɂ��ꂽ���ނł���悤�Ɏv���܂��B�@�o�ŎҁA�̔���ЁA���X�A�}���فA�ȂǏo�ŋƊE�œ��ꂳ��Ă��镪�ނł���Ə�����Ă��邱�Ƃ�����A���ʂɓK�������ޖ@�Ȃ̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��i�����͑z���ł��j�B
�i3�j�g�[�n���Ǝ��̕���
�@���X�ł̓X����y�ъǗ��ɂ����ẮA��ł܂Ƃ߂��A���{�\�i���ޖ@����{�}���R�[�h�͌����Ă��Ȃ��ʂ�����܂��B�����ŁA�g�[�n���͓Ǝ��ɕ��ޕ��@��ݒ肵�A�⊮���Ă��܂��B�����I�R�[�h�ƌ����܂��B
2.���Ђ̗l�X�ȕ��ޖ@
�@�O��܂Ƃ߂��u���ރR�[�h�v�̂Ƃ���ŏ����G�ꂽ�A�u�̔��ΏۃR�[�h�v�Ɓu���s�`�ԃR�[�h�v�ɂ��āA���̕��ނ̂������܂Ƃ߂܂��B
�i1�j�̔��ΏۃR�[�h�ɂ�镪�ށi���ރR�[�h�ɂ������̈ʂ�\���j
�@�̔��Ώۂɂ�鏑�Ђ̕��ނ́A���X�����ł̎����ɖ𗧂��܂��B
�@�����ł̕��ނ́A�S�Ă̏��Ђ��A���(0)�A���{(1)�A���p(2)�A���(3)�A�w�l(5)�A�w�Q�y�������z(6&7)�A����(8)�ɕ�������̂ł��B���Ȃ݂ɁA���ʓ��Ŏ������������e�X�̔̔��ΏۃR�[�h�ł��B�i2�j���s�`�ԃR�[�h�i���ރR�[�h�ɒu����S�̈ʂ�\���j
�@�P�s�{(0)�A����(1)�yA6��)�z�A�V��(2)�yB6����菭�����^�z�A�S�W(3)�A�o���E�p��(3)�y�����ނ̎����ɂ��ďW�߂����ЁA�܂��͑����ďo�ł��铯���ނ̂��́z�A���T�E���T(5)�A�}��(6)�A�G�{(7)�A�}�C�N���_������(8)�A���̂悤�ɕ�����Ă��܂��B���ʓ��̐����́A�X�̃R�[�h�ԍ��ŁA�n�t���p�[�������͕⑫�ł��B�����ŁA����x�u���ރR�[�h�v�ɐG�ꂽ���Ǝv���܂��B�@ISBN4-7631-8959-X
�@C0030�@ P1030E
�@|�@ ISBN�R�[�h�@�@ �@|�@ |���ށ@|�@|���i�R�[�h|
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �R�[�h
�@����������܂������A���ꂪISDN�R�[�h�ł��i��قǏ������A��̈ʁA�S�̈ʂ̂Ƃ���Q�Ɓj�B���ރR�[�h�̂Ƃ���ɒ��ڂ��܂��ƁA�b�̂��Ƃ�4���̐����ɂȂ��Ă��܂��B
�@���āA����������܂������A�u���ރR�[�h�v�́A�����ł܂Ƃ߂��ӂ��ƁA�ڂ����͐G��Ă��Ȃ��̂ł����A�u���e�R�[�h�v��3�̕��ނ���Ȃ�R�[�h�̌n�ł��邩��ł��B���Ȃ݂ɁA���e�R�[�h�ł����A���{�\�i���ޖ@(NDC)�Ƃ͈Ⴂ�܂����A�����悤�ɁA���e�ŋ敪���ꂽ�R�[�h�̌n�ł��B
�@�����ŁA���܂łł܂Ƃ߂����Ƃ���A�Ⴆ�A�u��ʏ��v�u���Ɂv�u���j�n���v�u�`�L�v�Ƃ��������̖{�̃R�[�h�́A0123�A�ƕ\���܂��B
�@�����Łu0�v�͔̔��ΏہA�u1�v�͔��s�`�ԁA�u2�v�͓��e�̑啪�ށA�u3�v�͓��e�̏����ށA��\���Ă��܂��B(�����ŁA���ރR�[�h�\�Ƃ������̂������܂�)
�@�����܂ł̂܂Ƃ߂ł́A���̕��ނ͖{�̒��g�Ɉ˂���̂���ł������A�O�������ʂ��镪����������܂��B�\�����d�����̂��n�[�h�J�o�[�A��炩�����̂��\�t�g�J�o�[�Ƃ����悤�ɓ�ɋ�ʂ��Ă��܂��B�����A����Ɋւ���R�[�h�̌n�͂Ȃ��悤�ł��B
��2�́@���Ђ̗��ʏ����ɂ����i�o47�j
�@����́A���Ђ𗬒ʏ�̏����ŕ����Đ������܂��B1.�ϑ����x�Ƃ́i�o47�j
�@�������ɁA�����Ƃ��āA���߂�ꂽ�������ɂ����Ă̕ԕi��F�߂�Ƃ������x�������܂��B����͈ȑO�ɂ��������ڂ����܂Ƃ߂Ă���܂��̂ŁA��������Q�Ƃ��Ă��������B
�@�ϑ��ɂ͂�������ނ�����܂��B���ɂ܂Ƃ߂܂��B
�i1�j�V���ϑ�
�E ���ʏ����F�ϑ��@�E�������@�F����
�@�V���������A�܂��͏d�ł���鏑�Ђ��V���ϑ��i�Ƃ���A���X�ւ̈ϑ����Ԃ��݂����܂��B���Ԃ͒ʏ�R�������ł��B�������A����͔̔���Ђւ̓��������ł�����A�A���ɗv����������������ĕԕi����K�v������܂��B
�i2�j�����ϑ�
�E���ʏ����F�ϑ��E�������@�F����
�@���łɊ��s���ꂽ���̂��e�[�}��G�߂ɍ��킹�ăZ�b�g�g�݂��A�ϑ����Ԃ��������̂��A�����ϑ��i�ł��B�����́A6�����������Ƃ��܂����A�Z���ԁi4�����j�̂��̂�����܂��B�����ϑ��i�Ɋւ��ẮA���ꂽ���͕̂�[�����ɔ�����ςȂ��ɂ��邱�Ƃ������Ƃ��Ă��܂��B
�i3�j������
�E���ʏ����F����@�E�������@�F����
�@���̐��x�́A���i�Ƃ��Ă͈ϑ��ł����A�Ŗ���A�o�ŎЂ̎ЊO�Ɉ����̂��ߊ���Ƃ������t���g���Ă���悤�ł��B
�@�܂��A����Ƃ������t���Ӗ�����̂́A��ɏ��X�ɒ��A�Ƃ������Ƃł��B���̂��߁A���̏��i�ɂ͏����[�J�[�h���}������Ă��āA���ꂽ�炷���ɒ������A��[���܂��B�����Đ��Z���ɑS���ԕi�������ƂȂ��Ă��܂��B
�@�������A����ł́A��Ɍ_�̍������ԕi�Ƃ��ďo�ŎЂɕԂ���邱�ƂɂȂ�A��p�������݂܂��B�����ŁA�ԕi�����̖�ꃖ���O��������[�J�[�h��ۗ����A�X�g�b�v���܂��B�Ȃ��A��[�́A�o�ŎЁA�܂��͔̔���ЂŋL�^����Ă��āA���N�x�̌_��X�V���̎Q�l�����ɂȂ�܂��B
2.���ɂ��āi�o50�j
�@��ł��܂Ƃ߂��A�ϑ��ɑ��āA���Ƃ������x������܂��B�ԕi��F�߂Ȃ��A�Ƃ����̂����̓��e�ł��B
�i1�j����
�@�����ł́A���ɓK�p����鏤�i�������Ă������Ǝv���܂��B
�@�E���؈��V����
�@�E���؈��\�������s��
�@�E�q���A���X�̌��������A��[�̒����i
�@�E�̔���Ђ̔��X�ł̍w��
�@�܂��A�V���ϑ��i�ł��A�z�{��̒����Ɋւ��ẮA���؈����ɂȂ�܂��B
�i2�j�����ɂ���
�E�K�p���x�F���@�������@�F����
�@�i��̐�������ʏ�����������邱�Ƃ������Ƃ����܂��B
3.�R�����F�ϑ����x�ƕ�[�V�X�e���i�o49�j
�@�������̂Ƃ���ŐG�ꂽ��[�X���b�v�ɂ��Ă܂Ƃ߂܂��B
�@��ł��܂Ƃ߂܂������A�ϑ����x�ɂ����Ă͌��߂�ꂽ�������ɂ����Ă̕ԕi���F�߂��Ă��܂��B�܂�lj������Ɋւ��ẮA�ԕi���F�߂��Ȃ��Ƃ������Ƃł��B���̂��߁A���X�͎���d����ɏ��ɓI�ɂȂ�X��������܂��B�@�@���̉��P��Ƃ��āA��[�X���b�v�����܂�܂����B�����ʼn��Ƀ����b�g�ƃf�����b�g�������܂��B
�����b�g
�@�E���X�͔��ꂽ���i��c���ł��A����������������g�p���邱�Ƃɂ��e�Ձ@�@�ɂȂ�
�@�E�o�ŎЂ͏��X�̒lj������p�x�̏㏸�ɂ���ď��X�X���ɂ������ꏊ���@�@�Ċm�ۂł���
�@�E��[�X���b�v�ɂ�钍���͔��؈����Ȃ̂Ŏx�����������s����B
�@�E���X�͔������鏤�i�����ԓ��ł���A���؈����ł����Ă��A�ϑ��d����@�@�Ƌ�ʂł��Ȃ����߁A���ʂƂ��ĕԕi�ł���
�f�����b�g
�@�E�lj��������e�ՂɂȂ������ƂŁA�ߓx�̎d����̌����ƂȂ�A�ԕi�������@�@�ނ����ꂪ����
�@�{�����܂Ƃ߂�Ƃ��̂悤�ɂȂ�i�Ǝv���j�̂ł����A�����b�g�̂Ƃ���ŁA�x�����������s����A�Ƃ���̂ɁA���ʂƂ��ĕԕi�ł���A�̂ł���A�o�ŎЂ́A�ԕi�ɍۂ��āA�ԋ����s���Ƃ������ƂɂȂ�̂ł��傤���B�������^��Ɏv���܂����̂ŁA�ۑ�ƒv���܂��B
����3�́@�������x�ɂ����iP52�j
1.�����̂����݁iP52�j
�@�ǎ҂́A���X�֒������Ė{�����邱�Ƃ��o���܂��B���̏ꍇ�A���X�͔̔���Ђɔ��������܂��B�̔���Ђ́A���Ѝɋy�яo�Ŏ҂��璲�B���ď��X�֑��i���܂��B������u�������x�v�Ƃ����܂��B
2.�����i�Ƃ́iP52�j
�@���X���̔���Ђ֔����������i���A�u�����i�v�ƌ����܂��B����ɂ́A�ǎ҂����X�֒����������i�E���X���X�����i���[�������邽�߂̏��i�Ƃ�����܂��B�����ɂ������ẮA���ҁA����̒����Z�����g�p���邽�ߌ����ɓ����ʂ��邱�Ƃ͏o���܂���B
3.�����[�̎�ނƖ����iP52�j
�i1�j�q����p�����[�@�@�F�ƊE�����Đ��x���������́B�̔���Ж��ɐF�����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����Ă���B
�i2�j���В����[�i���Z�j�F�X�����i�̕�[�p�Ɏg���Ă���B
�i3�j���ȏ��̗p�i�����[�F�w�Z�̋��ȏ��╛���ނȂǁA�ꊇ�̗p�̍ۂɎg�p�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�B���ʐv����v����̂ő傫���ڗ��悤����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Ă���B
�i4�j�����[�J�[�h�@�@�F�������i�ɕK���}������Ă��钍���p���B
�i5�j�K���}���J�[�h�@�@�F���X���A���ȍɏ��i�Ƃ��ď���鏤�i�i�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�K���}���j�Ɏg�����ߏ����[�J�[�h�Ɠ��l�̋@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�\�����������B
�i6�j�����[�����[�@�@�F�S�Ă̏��Ђɑ}������Ă���B��܂�ɂ���ā@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���āA��Ђ���[�����p�A������Ђ�����J�[�h�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ƂȂ��Ă���B
�i7�j�����[�@�@�@�@�F�̔���Ђ����ʂɈē����A�\�����݂���钍���[�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�B
�i8�j�ꗗ�\��[�������@�F�������ꗗ�ɕ��ԁB�ꊇ��[�����p�Ƃ��č쐬���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ꂽ�B�ژ^�┄�ド���L���O�ɂ��ƂÂ����{�����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����˂Ă���B
�i9�j�d�b������p�����[�@���ɂ�����悤�ł����A��肠�����͂��ꂾ���o���悤�Ǝv���܂��B
4.�����[�̗���(P55)
�@�ȒP�ɗ���������Ă����܂��B
�E�i���X����j�����[��t���E�_�����E�����[�d�E�i�o�ŎЂ���j�W�i�A�܂��́i�̔���Ђ���j�o�Ɂ��E���ލ�Ɓ��E�l���i���i�`�F�b�N�j���E�N�[���E�o��Ɓ��E���X
�@�ƂȂ�܂��B
�i1�j�e�함��
�@�g�[�n���ł́A��s�����ɂ��钆�������͑S���K�͂ŕ��L�����i�Ǘ������A�u���Ɂv�u�R�~�b�N�v�Ȃǂ͓Ɨ������e�Z���^�[�Ƃ��āA�n�����_�ł́A�u�������W�X�e�B�b�N�Z���^�[�v���ғ����Ă��܂��B
�i2�j���̓`
�@�ŏI�I�ɒ��B�s�\�ȏꍇ�́u���̓`�v�ƂȂ�܂��B���̏ꍇ�A�����p���͏��X�֗��R�L���ԋp����܂��B�u���̓`�v�ƂȂ�̂́A���Ǖs�\�E�i�E��ŁE�����E���s�\��x���E�Y�������Ȃ��E�����s�����E�s�����i����Ȃ��j�Ȃǂł��B
5.�R�����F��ƃR�[�h(P54)
�@�g�[�n���ł́A�����i�����X�ʂɕ��ސ������đ��i���Ă��܂��B�e���X���ɁA���ދL��������A��ƃR�[�h�ƌĂ�Ă��܂��B
����4�́@������s���ƒ������(P56)
1.������s���Ƃ�
�@�S�W��V���[�Y���̂ȂǁA����I�Ɋ��s����鏑�Ђ������܂��B�P�s�{�Ƃ͈Ⴂ�A�V���[�Y���ɒ���I�Ɋ��s����A�e�[�}���W������������̂��̂荞��ł��āA���{�`�Ԃ������ŁA�艿���ގ����Ă��邱�Ƃł��B
2.�������
�@���X�ɖ����i����j���܂��đ����Ă���������������Ƃ����A��������́A����s����\��ǎ҂̕ϓ��ɂ���ĉ������܂��B��������X���Ƃ����A�u���В�������\�����v�ɂ���čs���܂��B
|