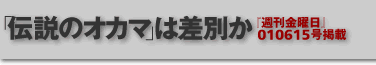 |
 |
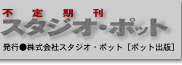 |
| その6「抗議」が議論と出会うとき 「伝説のオカマ」論争を「あす」に活かす |
[2002年02月22日] |
|
●第07回(最終回) 平野広朗 |
アンチ・ヘテロセクシズム つまるところ、要は闘うべき敵を過たずに見据えることだ。 今回の「論争」の中で、「すこたん企画はゲイの内部に向かないで、『外』にばかり向いている」という不満の声を聞いた。発言者に真意を直接確かめてみたい気はするけれども、「外」を向くこと自体を悪いことだとは、ぼくは思わない。ぼく自身もどちらかと言えば、「外」に向かって発言をしてきた。ゲイを差別・抑圧している社会に問題があるのだから、「外」に向かってその病理を問い質すのは当然のことだ。 「外」に向かって活動を展開するときの基本は、「外」に呑み込まれないことであろう。「世間」の価値観・「常識」といったものに対する疑いの眼差しを、常に曇らせないでいることである。たとえば、些細な例を挙げると、ぼくは今まで、自分のプロフィールなどに出身大学名を書いたことがない。教師をやっている以上、大学を卒業していること、そのことによって恩恵を被っていることは隠しようのないことだけれども、それをそのまま書き連ねることには抵抗があるからだ。「それがそれほど大したことか」「普通、誰でも書いてることじゃないか」という意見もあるかもしれないが、学歴という物差しで差別が正当化されている社会構造の中で、リベレーションの場にまでそんなものを持ち込むような愚を犯したくはないと、ぼくは思う。些細なことであろうと、多くの人がなんとも思わないことであろうと、「フツー」「常識」といったものを一つ一つ疑ってかかるだけの感性を持ち合わせない者に、差別と闘い抜く力があるとは思えない。権威主義は、権威に対する弱さの裏返しなのだということに気付かずして、はたして敵を見据えることができるだろうか。 「外」に向かってものを言うとしても、「ぼくたちはこんなにも差別されてるんです」などという言い方を、ぼくは極力しないようにしてきたつもりである。「被差別のしんどさ嘆き節」を垂れ流せば一時の慰めや励ましは得られるかもしれないが、所詮、それは一段高い所にいる者から施される「同情・憐れみ」でしかない。いくら嘆いて見せようと、彼ら異性愛者が自らを問い直して、ヘテロセクシズム社会を変革するための共同戦線に共に立とうとしないならば、何の意味もない。それが証拠に今回の件で、『週刊金曜日』が伊藤悟・すこたん企画の側に立とうとしたのは、「かわいそうなゲイ」を「守ってやる」立場にいるほうが気持ちがいいからであって、共同戦線に共に立とうとしたからではない。その他の「当事者」に冷たかったのは、異性愛者と対等な立場から発言をしようとした「強い(?)ゲイ」に対してでは優位に立てないからであって、彼らは相変わらず「向こう」に立ったままでいる。かくして、差別の構造は温存された。 「かわいそうなゲイ」のイメージに甘んじているなんて、ぼくにとっては我慢ならないことである。「自分の及ばない力によって規定されてしまう無力な存在」でいるなんて、まっぴらだ。リブの運動を始めて何年にもなる人がいつまでもビービー泣いているのを見るのは、正直言って、見ているこっちのほうが恥ずかしい。 「慰めを施されるかわいそうなゲイ」は、そこに留まる限り差別を温存するものだ。差別を温存しておかなければ慰めてもらえないのだから。そして、いつまでも「こんなにも差別されてるんです」「こんなにも大変なんです」と訴え続けることは、知らず知らずのうちに「差別されている境遇」を自分の居場所にしてしまう危険性を抱え込むことになる。訴えたり「抗議」したりすることそのものに、自分の存在意義を見てしまうのである。「差別と闘う」という大義名分を掲げる快感に酔って、差別と闘っているつもりが「差別されること」を必要とするようになってしまうのだ。こうした運動家は「被差別者」の位置《クローゼット》から出てくることはないだろう。出てきたら、「すること」がなくなってしまうからだ。「運動依存症」のやっかいなところである。そうなったら、ヘテロセクシズム社会の思う壺だ。 「『外』にばかり向いている」という批判が以上のようなことを指していたのなら、ぼくも同意する。「外」に向かって闘っているつもりが、じつは「世間」と寝ていたことを見抜いての批判だったとしたら、慧眼であろう。卒業大学名や肩書きを麗々しく書き並べることと「理解ある異性愛者」に「慰め」を請うこととは、同じ線上に並ぶ。 原点に戻ろう。 「伝説のオカマ」論争は、自己肯定の基盤をどこに置くかという問題をぼくたちに衝きつけた、はずである。記事の内容をどう捉えるか、「東郷健」をどう見るか、そして、「おかま」という言葉をどう受け止めるか、読者の姿勢が問われたのだ。ここで問われるのは、ぼくたちが「東郷健」をどう再評価するかではなくして、ぼくたちは「東郷健」のあとをどう歩くか、どう生きるかということである。 何度も言うように、若かりしころ、ぼくも「東郷健」には大いなる違和感を感じていた。「世間」の人々が「東郷健」を見る目で、ぼくも彼を見ていた。と同時に、自分も彼と同じように見られることを怖れてもいた。健さんを忌避しながら、人々が嘲っているのと同じものがぼくの中にもあることをどこかしら感じていたのかもしれない。「東郷健」を全面肯定するわけではないけれども、彼を忌避していた心の中に、「世間」の価値観にしっかり取り込まれてしまったぼくがいたことを、今のぼくなら否定しない。 彼が最後に選挙に出たときの政見放送を、偶然見る機会があった。何気なくつけたテレビに、健さんが映っていたのだ。昔なら、すぐさま消してしまっていたかもしれない。だが、そこにぼくが見たのは、「おかまの東郷健です」の語感が想像させるような「いかがわしさ」も「おどろおどろしさ」もなく、細面のおじさんが、ただただ訥々と語る姿であった。静かで穏やかな語りに思わず居住まいを正したくなるような、厳粛な瞬間《ひととき》。ひょっとしたら、ぼくたちは「食わず嫌い」だったのかもしれないとさえ、思う。かつてのぼくたちは、彼の何に怖れをなしていたのだろう。何を嫌っていたのだろう。 「伝説のオカマ」はぼくたちに、そんな過去の自分を思い出させる。 「世間」と一緒になって健さんを嫌悪し罵っていたぼくらは、トランスジェンダー/トランスセクシュアルを嫌悪し、オネエを嫌悪し、「おんな」を嫌悪していた。自分も「おかま」と見られることを怖れ、同列に見られることを怖れ、「男らしく」振舞うことに神経をすり減らし、「男らしい男」に憧れてきた。「世間」の価値観にがんじがらめに囚われて、差別に加担してきたし仲間を貶めてきたし、自分自身をも否定してきたのである。そうした過去の自分に対峙することは、正直言ってしんどい。「伝説のオカマ」は、内なるホモフォビアを暴き立てて見せる。「オカマ」というタイトルに傷付いたとすれば、それは、こういうことであるべきだ。 「おかま」という言葉に反応するとき、ぼくたちの内に潜むミソジニーとマチズモが蠢く。なぜ、ゲイに対して敵対的でない記事を読んでさえ「傷つく」のか。それは内面化してしまっているホモフォビアによって傷つけられるからである。敵は「外」にあるだけでなく、「内」にもある。だから、しんどいのだ。だが、「内なるヘテロセクシズム」を撃つことをしない限り、差別と闘う力が生まれてくることはあるまい。 このしんどさを乗り越えてこそ、「伝説のオカマ」論争の意味がある。ぼくたちの「あした」もある。自分自身の心のありようを真正面から見詰め直すとき、改めて、自己受容の深さが厳しく問われるだろう。差別との闘いは、自分自身との闘いでもあるのだ。 (2001.12.13〜2002.1.31。2.10一部修正) |
| ←「伝説のオカマ」は差別か topにもどる | page top ↑ |