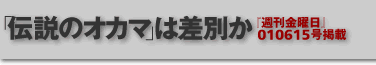 |
 |
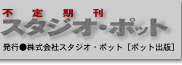 |
| コーナー●その5この問題を考えた | [2001-12-20] |
|
●その5-19 タカモリコウイチ
|
問題になった記事やシンポジウムとは直接関係ありませんが、「オカマ」という言葉の使用をめぐって考えたことがあるのでメールいたしました。映画好きとしては、伊藤さんたちのスタンスがまかりとおったら、映画を骨抜きにする可能性がある気がして、遅まきながら一言いいたくなりました。ぼくは映画が好きですから、映画についてお話しますが、別にこれは小説でも、演劇でもなんでもいいんじゃないかと思っています。 みなさんは、たとえばこんなシーンをどう思われるでしょうか? 飛行士が上官に戦況報告をしている (中隊長Aが別の上官、中隊長Bに頼む) 中隊長B:よし、わかった! (飛行士Aが前述の内容をゆっくり繰り返す。中隊長たちは依然として分からない様子) そこに飛行士Bがやってきて「別嬪の敵兵ですぜ! ムスコの出番だ!」など、ヘテロセクシュアルな性的興味をあからさまに叫ぶ。それに対して、飛行士Aは何を言っているのかさっぱり分からないというリアクション。 じつはこれは『空飛ぶモンティ・パイソン』の有名なギャグ。『モンティ・パイソン』っていうのは、実にあほらしいシュールなギャグを矢継ぎ早に次々と繰り出す芸風でイギリスから世界に飛び立ったコメディアン集団です。見てみると、女装ネタ、オカマネタが満載。それをなにかの機会に初めて目にしたぼくは、当時同性愛を扱ったことで大いに話題になった映画『モーリス』とはまったく違う、おもしろおかしいオカマを発見して一人密かに、喜んでいました。ゲイというのは隠してなくちゃいけないことだっていう感覚をもっていた当時のぼくにとって、『モーリス』はそのころのぼくの心に「共感」をもたらしたけど、『モンティ・パイソン』はそれとはまったく違う在り方に「驚き」をもたらしました。そして大笑いしたのです。果たしてぼくはゲイの差別問題をまったく知らなかった当時だから大笑いできたのだろうか? 実験をしてみました。つまりいま一度、見直したわけです。そして、いまみてもやっぱり大爆笑。表情など微妙なニュアンスが伝わらないとなかなか納得してもらえないかもしれないけれど(面白いから是非見てくださいね、『空飛ぶモンティ・パイソン』)。 いまになって知ったことなのですが、このモンティ・パイソンのメンバーには六〇年代終盤にカミングアウトして、七〇年代初頭にロンドンで「ゲイ・ニュース」っていう雑誌を創刊するのに一役買った人がいます。グレアム・チャップマン。彼は一時期フィアンセがいて、結婚する予定だったこともあるみたいですが、それが破談してからは、48歳の若さでガンで死ぬまでボーイフレンドと添い遂げたそうです。イギリスには多くのゲイの有名人がいるけれど、そのなかでもきちんとした人権運動を率先して行っていた人が作ったギャグだったのですね。道理で内部事情に詳しいわけですね。 そう思ってみると、ゲイだけがセックスのことばかり考えているわけではなく、そのあと異性愛者も出てきて淫乱な発言をしていて、「ゲイだけが特別に淫乱なんじゃない、おまえらノンケだって同じだろ?」というメッセージが聞こえてきそうです。よくある<ゲイ=セックス・モンスター>というステレオタイプを強化しているように一見見えながら、そうはなっていないんですよね。 ぼくは、こういうギャグは大幅に則を越えない限り大好きです。差別を根絶するというイデオロギーによって、こういう<毒>を持ったゲイ特有の笑いのセンス――自分を落としておいて、相手の急所を撃つ笑い――まで、取り上げられてしまうとなると、大いに悲しい。まるっきり面白くないノンケギャグだらけの『ブリジット・ジョーンズの日記』だけが笑いだというのは、文化的に貧弱だと思います(あ、『ブリジット・ジョーンズ〜』が好きな方を傷つけてしまいました)。ゲイが差別のなかをサバイバルしながら身に着けてきたことは、こうして多少の<毒>も笑いに昇華していく強さ、自分に対する敵意を微妙にそらし、笑いに回収しつつ相手の喉仏を打つしたたかさだと信じたい。モンティ・パイソンの新作はもう見られないけれど、これに類するオカマ的なギャグや表現――たとえば『サウス・パーク』や日本でいうとアッパー・キャンプ−−が、「オカマ」の一言で抑圧されてしまうような社会には生きたくないな、と思います。そういう政治的な意図がですぎた映画ってつまらないですしね。 そういうわけで、だれが使おうとメディアに出れば一人歩きする可能性のある言葉を抑圧するという非現実的な幻想を追うのはやめて、現実を笑いとして受け流せる余裕を持ちたいものです。どんな言葉でも人を傷つける可能性は孕んでいますし、あらゆる言葉を使うときに最も傷つきやすい人間からのメッセージだという宣言がなされるなんて考えられません。たとえばニュースキャスターがいちいち「私は交通事故にあったことのある人間で、その恐ろしさを最もよく分かっています。したがって交通事故という言葉を使用します」などと宣言をするニュース番組や、新聞社の記者やデスクがいちいち「当事者」である弁明をしている記事が山ほどあったりする新聞なんてありえないですよね。当事者であろうがなかろうが、悪意に満ちた表現は嫌なものだし、表現の対象に《愛》を感じれば、いわゆる<差別語>を使っていても、面白さ、誠実さ、生き様、さまざまなものが伝えられると思います。問題の『週刊金曜日』の記事は結局、差別をなくすためには、差別的な態度をとる人びとに対して、どれだけ多くの情報を流せるかということが大切なんじゃないか。あらかじめ予想されるステレオタイプな偏見や拒絶反応を回避するのではなく、モンティ・パイソンのように、そうしたものも引き込んで笑いのめす余裕があるといいのではないでしょうか。政治的で抹香臭い映画ばかり見させられるのと、<差別>も一気に笑いのめしてしまうような内面からこみ上げてくる活力があって、ぼくたちを元気づけてくれる表現と、どちらが見たいですか? そしてもう一つの最も恐れるべき選択は、政治的糾弾に恐れをなして、被差別者が描かれなくなってしまうことでしょう。私には、伊藤さんたちのスタンスで作られた表現から元気を得ることができるとは思えないのです。 ところで、伊藤悟さんたちは『モンティ・パイソン』や『サウス・パーク』に抗議したのでしょうか? 抗議のためのネタならたくさんありますし、世界中に出回っていますから『週間金曜日』より重大ですよ。 |
| ←「伝説のオカマ」は差別かtopにもどる | page top ↑ |