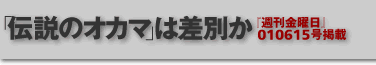 |
 |
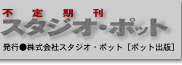 |
| コーナー●その5この問題を考えた | [2001-11-30] |
|
●その5-16 平野広朗 1955年生まれ。定時制高校教師。 ●この「誰が誰を恥じるのか」は、
|
有意義な議論をするために必要な視点は何か――六月十五日号の「東郷健」記事(及川健二著)に端を発した「おかま論争」を、ぼくはそんな想いで見つめてきた。とにもかくにも、議論が巻き起こったことは一歩前進と言うべきか。だが肝腎のことは、いまだ語られていないように、ぼくには思われる。 正直に言って、ぼくは『週刊金曜日』の熱心な読者ではない。今回初めて手に取って見たくらいである。とは言え、あの『週刊金曜日』が「東郷健」を採り上げるとあれば、いささかの興味は湧く。なぜ今「東郷健」なのか、いったい何を書こうとしているのか・・・件の記事を読んだぼくの感想は、可もなく不可もなしといったところだった。リアルタイムで「東郷健」を知っている者から見れば別段目新しいことが書かれていたわけでもなく、もっと突っ込んで欲しいところが不十分なまま残されたという印象も拭えないからだ。しかし、今この時期に「東郷健」を採り上げたことの意義は、決して小さくはないと思う。 ●「タブー」の人 健さんは一九七一年、初めて「おかまの東郷健です」と名告《なの》って選挙に打って出た。そのころ高校生だったぼくにとっては、「ショック」な事件だった。 そのころの「ショック」を今でも鮮明に覚えている人は、少なかろう。おそらく、多くの三十代以下のゲイにとって、「東郷健」は「過去の人」でしかない。ぼくの友人にも「知らない」若者が増えてきた。さらに、少なからぬ三十代半ば以上のゲイにとっては、「タブー」「忘れ去りたい存在」でもある。 それは及川記事のタイトル「伝説のオカマ 愛欲と反逆に燃えたぎる」が如実に物語る。まさに「東郷健」を語るにふさわしいタイトルだ。と同時に、ぼくたちゲイにとって複雑な想いを呼び起こさせるタイトルでもある。この言葉どおりの人生を歩んで来たがゆえに、彼は「タブーの人」となった。「大先輩です。尊敬しています」などと、綺麗事は言うまい。彼に対して違和感を抱いたゲイは少なくなかったはずである。 それでも彼は七〇年代〜九〇年代の日本を駆け抜けた。気に食わんところもあるおっさんだったが、彼がいなければ日本のゲイの「いま」はない。だからぼくたちは、こうしたアンビヴァレント(愛憎背反的)な心情を自ら見つめ直すことから出発するしかない。 おそらく彼は、「オカマを差別するな」という声を挙げた最初のゲイだった。彼を知らない世代が増えてきているこの時期、日本社会がどんどん右傾化していくこの時期に、天皇制に真っ向から反旗を翻したゲイである「東郷健」に再度向き合ってみることは、曲がりなりにも根付きつつある日本のゲイ・リブのありかたを考えるうえでも意味のあることであるに違いない。だが、議論は別のところから噴き出した。 決して「予想していた」わけではないけれども、やはり、伊藤悟さん(すこたん企画)から、抗議の声が挙がったという。「オカマ」という言葉をなぜタイトルに据えたのか、本文中の「オカマ」の説明が不十分である、「私たちは傷つきました」と言うのだ。 こうした抗議に対する「中身を読んで判断してほしい」という編集部の反論については、ぼくもちょっと待て、と思う。たしかに本文は差別的な内容の文章ではない。だが、本文を裏切るようなタイトルが、せっかくの立派な本文をぶち壊しにしていることが、日本のマスコミでは日常茶飯といっていい。ぼくも原稿を頼まれたときには、本文はもちろん、タイトル・小見出しに至るまで編集部で勝手に「改変」しないことを条件に出す。一九九一年に週刊誌の取材を受けたときも、写真のキャプション、電車の宙吊り広告・新聞広告の文言にまで十分な配慮をするように求めた。そのくらいまでして身を守らなければならないほど、日本のマスコミは売らんかなの商業主義に毒されている。取材者と被取材者との間の信頼関係や善意が踏みにじられることも珍しくない。 そういう意味で、今回すこたん企画が「伝説のオカマ」というタイトルにこだわって抗議したことは、理解できる。 だが、それでもなおかつ、ぼくはこのタイトルを支持する。むしろ、ぼくなら「伝説のおかま 東郷健」と一括りにして「 」を付けたろう。ぼくにとっては、「東郷健」イコール「伝説のおかま」なのだ。切っても切り離すことはできない。「東郷健という現象」を抜きにして、「おかま」というタイトルだけを論ずることに意味があるとは思えない。 「おかま」という言葉は、「東郷健」という存在とともに多くのゲイにとって「タブー」である。記事のタイトルに掲げれば当然、「火種」を抱えることになる。それでも著者と編集部はあえて、この言葉をトップに据えた。言論人としてアッパレと言っていい。抗議に対しては正々堂々と向き合うべきであろう。 ●議論されたこと、されなかったこと すこたんの抗議を受けて、『週刊金曜日』では八月二十四日号で「性と人権」という特集を組んだ。不満はいろいろあるけれど、特集が組まれたことに関しては、多としよう。 一読して考えさせられたのは、佐高信さんの「『個』が開かれたそれか、閉じられたそれかが問題になる」という指摘であった。健さんに遠慮したのか、佐高さんは「東郷氏が、閉ざされた孤だと決めつけるつもりはない」として、記事の書き方を問題にしているが、じつは記事はそこのところを期せずして「的確」に映し出していたのではなかったか。「東郷健」がノン・ゲイばかりでなく、ゲイの間でも多くの支持を集められなかった理由の一つはここにあったのだろうと、いまにして思う。 こうした視点については(ぼくたちゲイの間でも)かつて議論されたことがなかったように記憶するが、「これから」の運動のあり方を考える上で重要な論点となるであろう。 その他のページではどこを繰っても、「おかま」という言葉の使用の是非に関わる議論に、ほぼ終始しているようだ。要するに、抗議された編集員たちの右往左往ぶりばかりが目立つのである。だが、なぜ「おかま」という言葉が問題とされるのか、なぜ差別語として機能するのかといった肝腎のところは議論されずに終わった。残念である。 個人的にはぼくは「おかま」を、自称としても他称としても使わない。かつては蔑称であった「ゲイ」を、六〇年代アメリカのゲイ・リブがプライドをもった言葉として組み替えていったのに倣って、日本の一部ゲイ・アクティヴィストが自称として「おかま」を使い続けようとしていることは承知しているし、それについてとやかく言うつもりもないが、ぼくは使わない。理由は、この言葉がゲイだけに関わる差別語ではなく、ミソジニー(女嫌い)とマチズモ(男らしさ偏重)に関わる侮蔑語であると考えるからだ。 逆説的に言えば、落合恵子さんが紹介する「フェミニスト」たちの、「おかま」という言葉に対するこれほどまでの無邪気さが、ぼくには不思議なことに思える。「おかま」問題は、ほかならぬ異性愛者自身が取り組むべき問題なのだ。 「おかま」という言葉は、じつにいい加減で無責任な言葉である。「正確な意味」など誰も知らない。人と所と場合によって、意味も使われ方もさまざまだ。ざっと数えて十ばかりの意味をもっているだろうとぼくは考えているが、それぞれの意味内容の境界線も曖昧だ。だが、差別的に使われるときに共通するのは、相手の「おとこ性」を否定する機能をもつことである。「おんな」「女性的なるもの」を貶め、「おとこ」「男らしさ」に過剰なまでの価値を置いてみせるミソジニーとマチズモの土壌の中で、「おかま」は差別語として機能する。つまり、セクシュアリティに関わる言葉であるより、より「ジェンダー」に関わっての言葉であろうとぼくは考える。 今までもさんざん指摘してきたように、こうした視点を欠いた「用語解説」にぼくは同意できない。今回、伊藤悟さんは及川さんの「説明」を批判しているが、他人の批判をする前に、かつての自分の考察不足を自己検証しておくべきであったろう。 ●「当事者/非当事者論」の陥穽 今回の議論の中ですこたん企画は何度か、当事者が「オカマ」と言う場合とそうでない場合とでは「似て非なること」であるといった主張を展開している。一見もっともらしく聞こえる論法であるし、さまざまな場において主張される論である。しかし、多くの場合、いったい誰が「当事者」なのかという議論が置き去りにされてしまう。ことに今回は「ゲイ」を巡る問題だ。すべてのゲイがカムアウトできるわけではない、むしろ多くのゲイが「押入れ」に閉じこもっていることは、伊藤さんらも指摘しているところである。 だったら、「ゲイ」を巡る問題について発言している人のうち、誰が「当事者」で誰がそうでないと、誰がどうやって判断を下すのか、誰にも答えられないはずである。及川さんがゲイなのかゲイでないのか、ぼくは知らない。知らないが、本人の口から「告知」がないからと言って、「お前はノン・ゲイだろう。『おかま』という言葉を使うな」と決め付けるような傲慢な振る舞いをぼくはすまいと、自戒を込めて思う。 「当事者が使う場合とそうでない場合とでは、似て非なるものがある」というものいいは、あまりにナイーヴだ。これでは「既カムアウト者」だけが発言を許されることになってしまう。それでは「言論の独占」だ。常々言っているように、ぼくはむしろ「ゲイの言動(表現)であろうとノン・ゲイのそれであろうと、いいものはいい、悪いものは悪い」という原則に立つ。前述したような視点に立つことのないゲイが発した「おかま」より、ミソジニーとマチズモの問題を見据えたノン・ゲイの「おかま」発言のほうをぼくは支持する。 件の記事では、及川さん自身がこのタイトルを付けたというのだから、彼本人の主張・見解なり釈明なりが求められてしかるべきであった。にもかかわらず、「PTA」(編集委員・部員)だけがしゃしゃり出てきたのはどういうわけであったのか。そればかりか、「当事者」を大事にするという掛け声とは裏腹に、すこたん以外の当事者を排除した前回の特集は、多くの当事者の猛反発を買った。 あのタイトルによって傷付いたと言う人の訴えは、もとより重く受け止めなければなるまい。だがぼくは、傷付けられた人の「心に寄り添う」ことと問題の本質とを混同して、そこに留まっているわけにはいかない。 ぼくの関心事はもう一歩先にある。ゲイに敵対的でない記事を読んでさえ傷付いたとすれば、それはなぜかという問題である。その場から逃げることなく傷付いた心の内面を見つめ直したとき、いったい何が見えてくるのか。それこそを(ゲイ自身の)問題として立てたいのである。 健さんがゲイの仲間から浴びせられてきた罵声とも、レズビアン&ゲイパレードの「派手派手しさ」に対して毎年囁かれる仲間内からの「顰蹙」とも通ずる、「内面化されたホモフォビア(同性愛嫌悪)」をぼくはここに見る。かつて健さんを苦々しく思っていたぼくの内面に、「そう思わせる」世間の価値観が巣食っていたことを、今のぼくは否定しない。「おかま」と言われて傷付き萎縮してしまうのは、ミソジニーとマチズモに囲い込まれた社会の価値観を内面に取り込んでしまっているからだ。ホモフォビアを内面化してしまうことで、ぼくたちは「自滅」する。 前回の特集について、「虐げられたゲイ」と「理解ある異性愛者」との偽善関係を指摘する声もゲイの間から出されていたが、的確な判断であろう。傷付いて涙しているだけでは多数者の優越感を満足させ、ひいてはヘテロセクシズム(異性愛優位主義)社会に加担することになってしまう。辛いことかもしれないが、「内面化したホモフォビア」を撃たずして、ぼくたちの「あした」はない。いつまでも泣いてなんかいられないのだ。 |
| ←「伝説のオカマ」は差別かtopにもどる | page top ↑ |