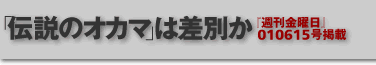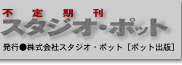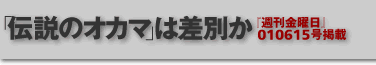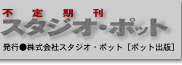|
【手紙掲載にあたって――サイト編集部】
グラウチ風子さんから、ポット出版に以下のようなメールが届きました。
このサイトへの投稿ではかなったのですが、書かれた内容からしてぜひサイトで公開したいと考えて、掲載のお願いをしました。
グラウチ風子さんから了解してもらったので、公開します。
(編集部・沢辺 01-11-01)
【グラウチ風子さんの手紙】
東郷健氏について及川健二氏の書かれた記事、「伝説のオカマ 反逆と愛欲に燃えたぎる」について、私的な経験からどうしても言っておきたいことがあります。「オカマ」という言葉をめぐる議論からはずれてしまうので、投稿の形はとりません。当初、及川氏への手紙として出そうと思っていたのですが、そうすると他の人が目を通しにくくなります。ポット出版の近辺にいらっしゃる興味のある方で読んでいただければと思い、このような形をとりました。お忙しいところ、申し訳ございませんが、ご一読いただければ幸いです。
東郷氏が「オカマ」と自称したことを考えるときに、どうしても落とせないもう一本の糸があります。この場で展開されているのが「オカマ」という言葉をめぐる議論である以上、無理はないと思うのですが、この点に触れないと、東郷氏が「オカマ」という言葉をあえて使った重みが伝わらなくなってしまうと思います。
これはすこたん企画さんが週刊金曜日に抗議したとき、第一の理由としてあげた
(1)(この記事に)伝説のオカマを使う必要はあったのか。
への遠まわしな反論ともなるはずです。投稿した文章ではこの点をスキップしました。論点が複雑になることを恐れたからです(前置きが長くてすみません。以下本文です)。
〈内在化されたタブーの恐さ〉
「不敬イラスト」と言ってしまう。それでは伝わらない。「昭和天皇がマッカーサーに犯されるイラスト」。言葉にすればそれだけのものだ。だがこれを公の媒体に載せようと決め、載せてしまったときの東郷氏の高ぶりを想像することは容易ではない。
「差別」と「タブー」は同じ軸上にある。何かを差別するな、と言われたとき、そのことによって自らを変えたくない人が取る一番安易な道が、それを「タブー」へと引き上げることだ。触れなければよい、使わなければよい。だがそれで何かが解決しただろうか。矢印の向きが変わっただけだ。「私」の存在は揺るがず、「私」は「私」で、「彼ら」は「彼ら」でしかない。そのような不可視に押しやられた包囲を切り裂くひとつの道は、自らその言葉を使い、誇りを持って振舞うことだ。東郷氏が行ってきたように。その行為によって最底辺を切開する。まずは、よし。
軸の先を辿ってみる。だが今度は方向が逆だ。最底辺の位置から見上げると、一番天井に何かが見える。誰かが誰かを差別し、差別された誰かが、また誰かを差別する。本当に撃つべきものはなんだろうか。差別した誰かではない。崩さなければいけないのは、果てしなく続くこの階段なのだ。
「差別」と「聖別」は紙一重だ。どちらも、「私」と「彼ら」を隔てる壁でしかない。東郷氏はその両端をはずそうとしたように私には思える。「オカマ」と呼ばれている最底辺の人間が、普通の人間でしかないのなら、「天皇」と呼ばれる最高峰の人間も、また普通の人間でしかないはずだ、と。だがそれは安易な道ではない。
私的な経験について書く。
およそ一年前、ひとつの物語が私に「降臨」した。正確に言えば、孕んだのは10年前だ。この10年間というもの、その物語は私の扉を叩きつづけた。本業の方で、これも10年がかりの仕事を終え、一息ついていた私の筆は勝手に動き始めた。私はその衝動に従い、「少年」の物語を書いた。最底辺の役割を押し付けられることで、不可視のシステムを支えつづけてきた少年の物語を。物語は進み、彼は「拉致」された。私がそう望んだわけではない。物書きとしてはなはだ無責任な言い方であることは承知していても、そう書かずにはいられない。このとき、物語はゆうに1000枚を越えていた。一介の駆け出しに過ぎない私の力だけで、可能になったこととは到底思えない。
彼が「拉致」された場所は私に衝撃をもたらした。「お堀の中」。やめてくれ、と私は思った。どうして、自衛隊基地じゃいけない。警視庁でも、右翼の黒幕でも、JCIAでもいいじゃないか。だが物語はいうことを聞かなかった。彼を大切に思う人たちが救出に乗り出した。作戦をたてるにあたって、私の筆は止まった。どうしても書かなければならない言葉を書くことができなかったのだ。いつまでも「お堀の中」と言ってごまかしていることはできなかった。
私の状況を再度確認しておく。私は小説家ではなかった。どこかに発表する宛があって、書いているのではなかった。その時点で、その「小説」が人目に触れる可能性はほとんどなかった。無名の物書きの1000枚を越えるアクション小説を発表する場など、常識で考えてあるはずもない。それでもなお、私は3日間苦しんだ。物語が始まってから一日も休まず、憑かれたように書き続けた私の筆を止めたのは何か。「書きながらメモ」と名づけた執筆時の日記から引用しよう。
『いいんでしょうか本当に。紙の上のこととはいえ、皇居を襲わせるなんて。躊躇しています。そして気づくわけです。私の中にタブーがあることに。
天皇制は恐ろしいです。
たかがアクション小説です。人目に触れるという保証もありません。なのに、なのに、書けない。「皇居」という文字が。「天皇」という文字が。皇居を襲う、となぜはっきり書けないのか』
私は自分の中に存在している「菊のタブー」にこのような形で直面した。
私は何を考えていたのだろうか。パソコンの中にしか存在しない物語である。まさか右翼が個人のデータまで閲覧し、自宅を襲うと思ったわけではなかろう。それでも「皇居を襲う」と書くことにはとてつもない勇気がいった。今でもそうだ。この文章を書きながら、私は震えている。私はそれを切り裂かなければならない。私は「自分」を切り裂かなければならない。
東郷健氏が「昭和天皇がマッカーサーに犯されるイラスト」を公共の媒体に載せたとき、その胸にはどのような思いが宿っていたのだろうか。それを想像することは私にはできない。だが恐ろしいまでの情念のたぎりを想像することはできる。その奔騰の中で計った場合、「オカマ」と自称することも、何かを撃つために東郷氏が選び取った手段のひとつと考えることができる。東郷氏のことを書いた記事に「伝説のオカマ」というタイトルを冠することは、彼の戦いを支援することだ。「反逆と愛欲に燃えたぎ」らなければ撃てない何かを東郷氏は撃とうとしていたのだろう。恐ろしいのは、それが己の身の内にガッチリと食い込んでいることだ。システムの中で育てられた人間が、そのシステムの犯した誤謬から自由であると思い込むこと。それは自分の立っている位置についての真実を覆い隠す、極め付きの罠だと私には思える。
|