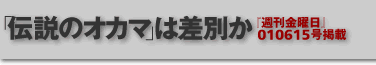 |
 |
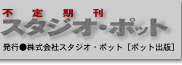 |
| その6「抗議」が議論と出会うとき 「伝説のオカマ」論争を「あす」に活かす |
[2002年02月15日] |
|
●第05回 平野広朗 |
尊敬すべき先達 これだけ説いてもなおかつ、「私たちは傷つきました」と伊藤悟・すこたん企画は言うだろう、か。 よろしい。では、なぜ「傷ついた」のか、はっきりさせようではないか。ぼくの睨んだところ、彼らの「傷」の正体は「(1)自分たちの目の届かないところで、(2)『週刊金曜日』が東郷健を採り上げたこと」にある。もちろん正直にこのような言い方はしていないが、「性と人権」特集ですこたん企画が書いていることを熟読すればわかることだ。彼らの主張を一番矛盾が少ないように読み解こうとすれば、このように解釈されることになる。 勉強会で「おかま」という言葉について十分に話しておいたにもかかわらず、その内容が「生かされなかった」として憤慨する気持ちは、ぼくにもわからないことはない。ぼくだって自分が話したことがまったく伝わっていないと感じれば、腹も立つ。気持ちはわかる。けれども、『週刊金曜日』はすこたん企画の下請企業でも、出来の悪い教え子でもないのだ。独自の立場から判断を下して自らの責任において発言をすることが、メディアの一員として求められているはずである。すこたん企画の言うなりにならねばならないいわれはない。 ところが、特集全体の構成からは「同性愛に関する正確な情報を発信している当事者団体」を自負するすこたん企画が、無知蒙昧な編集部(と読者)に「セクシュアリティの基礎知識」を教え授けるという構図が浮かび上がってくる。かつて『同性愛の基礎知識』(伊藤悟、1996年、あゆみ出版)が出たときにも、「基礎知識」などと銘打つことの出来る神経をぼくは疑ったが、そのときの「(ありがたい教えを垂れる)教師根性」とでも言うべき姿勢は今回にもそのまま受け継がれている。これでは、まるで「先生の言うことが聞けない子は悪い子です」の図ではないか。 『週刊金曜日』とすこたん企画は別の「人格」なのだから、すこたん企画はまず、編集部の意図を問うことから議論を始めるべきであったろう。勉強会のあとで、それでも敢えて「伝説のオカマ」をタイトルとして掲げた意図はなにか、と。「性と人権」特集では、自分たちの思い通りにならなかったことへの苛立ちと戸惑いが顔を出してしまっているが、本来ここで問題にされるべきは、すこたん企画の意思に合致しているかどうかということではなくして、このタイトルを採用したことが同性愛差別と闘う立場から見てどう評価されるかということである。 タイトルに「伝説のオカマ」を掲げた理由は、至極明快だ。それは、これが「東郷健」を採り上げた記事だからである。 「東郷健」こそは、「おかま」という言葉を全国に広めた張本人の一人であった。彼を取り上げた記事のタイトルに「おかま」の文字が躍っているのは、当然のことだ。タイトルはその言葉だけが独り歩きをする危険性があるからいけないとすこたん企画は言うが、「東郷健」も「おかま」を独り歩きさせた。彼だけが「おかま」を全国に広めた「元凶」であったかどうかはぼくにもわからないが、「おかまの東郷健です」をキャッチフレーズとして選挙に打って出たのだ。ほかの「おかま」とはスケールが違う。 そのために、彼はさまざまな罵詈雑言を浴びた。ノン・ゲイからだけでなく、本来は仲間であってもいいはずのゲイの間からでさえ、「かえって偏見を撒き散らす」「あんなのと一緒にされたくない」「あれでは選挙に勝てるわけがない」などなどの陰口を叩かれ後ろ指を指された。それでも健さんは、どれほど白い眼で見られようと罵倒されようと、頑として「おかま」の看板は下ろさなかったのだ。 そんな健さんを採り上げるのに、「おかま」という言葉を外して良いわけがない。「伝説のオカマ 愛欲と反逆に燃えたぎる」とはよくぞ言ったり。秀逸である。 「東郷さんは私たちの大先輩であり・・・先達として尊敬しています」とすこたん企画は書いているが、ウソを言ってはいけない。本当に健さんを尊敬している人ならば、タイトルに「オカマ」と謳われているからといって「抗議」などしたりはしない。「オカマ」というタイトルが気に食わないと言うことは、「東郷健」が気に食わないと言うことと同義である。すこたん企画は、正直に言ったらいいのだ。「私たちは『東郷健』によって傷つけられました」と。健さんの登場でどれだけ多くのゲイが「不快」な気持ちを味わわされたか、ある一定の年代以上のゲイならば、実感としてみな知っている。 ぼくはこの3年ばかりの間、東郷健さんが主宰するゲイ雑誌『ザ・ゲイ』にエッセーを連載してきたが、その発端となったのは、ぼくがあるミニコミ紙に書いた「誰が『初』でもよかった、のか?――愚直の人、東郷健」を健さんが面白がってくれて自分の雑誌に転載したことに始まる(1998年12月号)。ぼくはその中でこんなことを書き付けていた。「『なに・コレ?』というのが、初めて彼の存在を知ったときのぼくの偽らざる気持ちだった。・・・正直言って『見てはならないものを見てしまった』感じだった。鏡をのぞいてみたら、そこには世間様が嘲りの的にしている『おかま』が映っていた、とでもいうか。『おかまの東郷健です』に注がれる白眼視が、そのまま自分に向けられているような心地悪さ・・・」 文章の最後を「善良な市民ヅラなんか糞食らえ」を貫いた健さんの生き方に対する共感の弁で締めくくったとはいえ、親子ほども歳の離れた若造がこんなことを書いているのに、健さんは怒るどころか、「彼の正直な書き方私は好きである」というコメントを添えて自分の雑誌にこれを載せた。健さんとは、そういう人なのだ。みんなからこんなふうに思われていることは百も承知、むしろ、口先だけの「尊敬」などいくら並べられようと喜んだりする人ではないと、ぼくは信じている。 今回の「論争」の中で、何人かの人が「自分も東郷健さんによって心に傷を負ったけれども……」と言うのをぼくは耳にした。そうなのだ。これが健さんに対する、誠意ある「尊敬」というものであろう。「けれども……」以下が大切なのだ。かつては健さんの行動を苦々しく思っていたぼくたちが、その苦々しさを再検証して今の自分の生き方を見つめ直すこと、それは本来、ぼくたちゲイがして来なければならなかったことである。及川さんの「伝説のオカマ」は、そのことをしないままのうのうと生きてきたぼくたちの怠惰を衝いた。だから、「論争」が起きたのだ。上っ面の「尊敬」なんぞを口にしながら「抗議」するような「当事者団体」に引きずられて、「言葉狩り」程度のレベルで言い争いをしている場合ではない。 同じ「おかま」という言葉が問題になったとしても、「東郷健」が主役でなかったなら、「論争」もここまで大きくなることはなかったろう。数年前、オランダ人研究者のウィム・ルンシングさんが「東郷さんのような過去の運動から、もっと学んだほうがいいのではないか」と呟いていたのを、今になってぼくは噛み締める。 健さんが選挙に打って出たのは1971年だったが、それに続くように70年代にはいくつかのゲイ雑誌が発刊され、中ごろ以降にはゲイ団体もいくつか生まれた。それらが健さんの選挙出馬と直接の関係があったのかどうかはぼくにはよくわからないところだが、すべてが「おかまの東郷健です」以降に始まっていることを考えれば、まったく何も刺激を受けなかったということは考えにくい。いろいろ批判はあったとしても、「東郷健」以降、マスコミなどで「顔」を晒して発言できるアクティヴィストが出現するのは80年代末まで待たねばならなかったのだから、健さんの行動力には改めて感心するほかあるまい。 ヨーロッパに本部を持つIGA(現ILGA:国際レズビアン・ゲイ協会)の呼びかけに応える形で80年代半ばに始められた現在のゲイ・リブは、70年代の「東郷健時代」とは人脈的にも戦術的にも別物だと言っていいだろうが、この30年の間に日本のゲイ・リブは徐々に広がりを見せて、今では東京ばかりでなく大阪・札幌などでもいくつかのグループが活動を展開するまでになってきた。そして、パレードや映画祭が毎年開催されるほか、HIV/AIDSに関わってボランティア活動に積極的に参加するゲイも増えてきている。このように、ゲイ・バー界隈の「夜の世界」に留まっていた活動が「昼」にもその場を拡大してきたことは、この30年間の顕著な「成果」であろう。だが、目指すべき方向性や活動の問題点などについて、各グループやアクティヴィストたちの間で活発に議論が交わされるような状況にはいまだ至っていないように、ぼくは思う。そうした議論のきっかけになってこそ、この「伝説のオカマ」論争が活きてくるというものだろう。 87年夏に開かれたIGA日本支部総会では、「日本で唯一のナショナルセンターを目指す」南定四郎事務局長と、「一つの団体だけを頂点としたピラミッド型の運動は間違いだ」とするぼくらとが激しく対立して結局袂を分かったわけだが、「分断」の亡霊におびえて自由な議論を封じ込めようとした辛淑玉発言を聞いて、ぼくはこのときの論争を思い出す。「小山の大将」になりたがる者が、自由な議論を怖れて権力を独占しようとするのだ。多様な意見の存在を認めない閉鎖的な運動は、すでにして腐敗を始めていると言うべきであろう。 |
| ←「伝説のオカマ」は差別か topにもどる | page top ↑ |