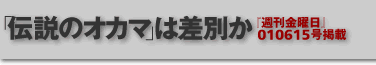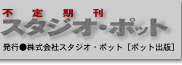|
〈存在しない「差別」に対する、存在しえない「抗議」〉1
週刊金曜日「オカマ」問題をめぐる一連の文書を読みつづけています。「オカマ」をめぐる松沢さんの文書は膨大ですが、筆者の無知を補ってくれました。この場を借りてお礼を申し上げます。
私は当事者ではありません。これまでの人生で、同性愛者の存在に触れ、それを含まないがごとく振る舞う世間に違和感を覚える(幸運な、と思っている)一人の異性愛者に過ぎません。私ごときに、この問題について発言する権利があるのかと何度も自問しました。それでもこうして文章をつづっているのは、事の起こりに対する違和感がどうしても拭えないからです。残念ながら私はロフトのシンポジウムにも足を運んでいません。地方在住、かつ家族に縛られている身としては、どうしようもありませんでした。経過には多大な興味と関心を抱いております。これからも、多くの人の視点から、この過程が明らかになることを楽しみにしております。
それでは手に入るかぎりの資料を元に、私の感じたことについて書いてみることにしましょう。
「傷ついたのは誰なのか」
タイトルに「オカマ」という言葉を使用することで、確実に傷ついていると断言してかまわない団体がひとつだけあります。
「すこたん企画」さんです。詳しくは「性と人権特集」の「私たちが声をあげたわけ」をお読みください。周辺情報を加えると、伊藤さんのこのときの態度は、大変感情的なものだったと推測されます。(それにしても、何故金曜日は「すこたん企画」への転載を承諾していながら、ポット出版への転載は拒否してきたんでしょうね。今まで二つのHPを行き来しなくてはならなかったので非常に煩雑でした。感情的な反応を排し、リンクを張られた沢辺さんの懐の深さに改めて敬意を表します)ウロコの部屋、5−4の内容と重なるので、引用は最小限にとどめます。
(1)本誌367号(二〇〇一年六月一五日)「シリーズ 個に生きる5 東郷健」(以下、「個に生きる」)のタイトルに「伝説のオカマ」を使う必要があったのか。
(2)「個に生きる」が掲載された号の発売2週間前(五月三〇日)、私たちは、『週刊金曜日』編集部の勉強会に講師として招かれ、当事者が「オカマ」という言葉を使うことと、非当事者(特に影響力の大きいマスコミ)が「オカマ」という言葉を使うこととは、似て非なることであると伝えた。その時、原稿もタイトルもほぼ決まっていたにもかかわらず、全く質問が出されなかった。それなのに、突然、上記タイトルが掲載されたこと。
(3)当該原稿の中の筆者の「オカマ」ということばの解説が間違っていること
(3)については松沢さんにお任せします。ウロコの部屋をお読みの方には、この指摘がいかに一面的なものであるかは明らかだと思います。ひとつ言えるのは、「すこたん企画」さんにとっては、「間違っていた」のだということ。それは彼らの引き出そうとしている結論、「オカマ」という言葉に傷つき、命を絶つことすらある、若い同性愛者が現実にいて「オカマ」という言葉を使用することで、この先もこういう存在を生み出してしまうかもしれない、という危惧、にそぐわないものだったということは理解できます。それを「間違っている」といってしまうこととはまた別問題であり、この辺の混乱がこの抗議の随所に見られます。ご自身の主張と真実が同じであれと願うことはできますが、同じであるかどうかということについては慎重にならなければいけないのではないでしょうか。「すこたん企画」さんの抱いている危惧が架空のものだとは思っておりません。危急、かつ深刻な問題だとは思います。ですが、なのです。
(1)については質問の意味自体が私にはピンときませんでした。「使う必要」とは何を意味しているのか。この点について、理解している方がいらしたら、ぜひ教えてください。(伊藤さん、よろしく、です)
で、(2)です。私にはこれが今回の抗議の確信であると思われます。感情的な確信。勉強会までした。「それなのに」…という思いが伊藤さんをはじめとする「すこたん企画」さんの方々に、このような抗議にもならぬ抗議をあえてさせたのだとしか思えないのです。(この抗議が編集権にかんがみて成り立たないものであることは、松沢さんによって論証されています。詳しい内容はウロコの部屋5−4をお読みください)
「オカマ」という言葉をタイトルに使用したことによって、セクシャルマイノリティである伊藤さん、あるいは「すこたん企画」の方々は傷つきました。しかし、「ある」マイノリティの人が傷ついたからといって、それがマイノリティ全般の人権を侵害しているかのように振舞うことは、カテゴリーの誤謬であるとしか思えないのです。マイノリティの人が傷つく、ということイコール、人権が侵されたからとは限らないのです。その辺を明らかにするために、「オカマ」問題とはまったく関係ない、ひとつの例を出します。
「『三杯目』問題」
これは私の家族におこったきわめて内輪の問題です。夫の母は視覚障害者で、障害者手帳第一級を保持しております。その意味で極め付きの「弱者」です。「同居」は最初からの条件でした。私は障害を持つ人と一緒に暮らしたことがなく、最初どう振舞えば彼女が傷つくのかがさっぱりわかりませんでした。たとえば、夫と義母と車に乗ったとき、窓から見えるものについて話すことさえ、私は恐れました(あの家きれいね、とかそういう害のない会話でもです)。義母の目にすることのないものについて話すことで、義母が疎外感を感じてしまうかもしれない、と思ったからです。さすがにそのような不自然な状態には耐え切れず、私の態度は徐々に通常に戻っていきました。そのころでしょうか、この事件が起こったのは。
夕飯の風景を想像してください。食卓を囲み、おいしそうに食べる家族。おかずの内容は忘れましたが、その日は誰もが御代わりをしました。空っぽになった茶碗を誇らしく思いながら、御代わりをよそう妻(私のことです)。どこにでもありそうなその光景が一変したのは、夫が三杯目の御代わりをしたときでした。よそおいなおした茶碗を夫に渡しながら、私は言いました。
「これで三杯目だね」
解説する必要もないほど、どうということのないせりふでした。ところが、その途端、食卓の空気が一変しました。義母の割れがねのような声が響き渡ったのです。
「人が何杯食べようといいじゃないの。何杯目なんて言うんじゃありません!」
それはまさに悲鳴とも呼ぶべき、感情的な叫びでした。食卓は凍りつきました。義母のわけのわからない非難に、私は傷つきました。義母が集団疎開で食べ物について深刻なトラウマをもっていることは、後で夫が解説してくれました。それ以来我が家では「何杯目」という言葉は発禁状態です。なぜなら、その言葉を使うと、弱者である義母が傷つくから…。
笑ってください。笑っていただいた方が気が楽です。私がこんな家庭内のどうしようもない出来事をさらすのも、皆さんにわかっていただきたいためです。
「三杯目」という言葉がマイノリティである義母を傷つけた。それが確かです。でもそれは視覚障害者の人権を侵したからではないのです。義母は義母の心に抱えたトラウマによって傷ついた。それはもしかしたら、視覚に障害を持っているという事実から引き起こされたものかもしれませんし、そうでないかもしれません(目が不自由なために食べ物にありつけなかったとか)。それはわかりません。それでも、マイノリティという立場にある人を傷つけたマジョリティである私には、反論することが非常に難しいのです。
私は義母に感謝しています。「弱者」という立場に安住することによって、いかに人は強者となれるかを余すことなく教えてくれた義母に。その義母の子供として生まれた夫がこうむった人権侵害は、本当にひどいものです。30も近い男の休日が、すべて義母の医者廻りで潰されるとか、ひどい事例には事欠きません。私は黙っていられるような人間ではありませんから、義母と徹底的に戦いました。視覚障害者の姑をいじめる、鬼嫁といわれようと一向に構いません。私は好きなようにやっています。夫もだいぶ自由になったようです。母はボランティアさんとお茶を飲みに行くまでになりました。
「マイノリティ」の人に傷つかれると多くの「マジョリティ」は弱いものです。それが「人権擁護」などという錦の御旗を掲げていらっしゃるメディアの方々でしたら、なおさらでしょう。私は自分のことを善人だとも、正義の味方だとも、ちっとも思っておりませんから、そこから抜け出すことができましたけど。けれど、これだけは声を大にして言いたい。どうか、ゆめゆめお気をつけて。ある「マイノリティ」が傷ついたことは事実でも、それが人権に関することなのか、その個人のトラウマに関することなのか、それを見極めようとする勇気を持たなければならない、と。
差別的な使用ではない「オカマ」という言葉に、「すこたん企画」さんが傷ついたのは何故なのか。ねえ、週刊金曜日さん、もう一辺考えてみたらいかがですか。
追伸(主に、「すこたん企画」さんへ)
もういっぺん書いておきますが、学齢期の同性愛者が「オカマ」という言葉で傷つけられているということを否定するわけではありません。ただその問題はいじめる子供も含めた学校というシステムにおける問題として捕らえることが必要だと思います。まさかとは思いますが、「オカマ」という言葉を使わなければ、その種のいじめは起こらないなどと考えていらっしゃるわけではありませんよね。
〈存在しない「差別」に対する、存在しえない「抗議」〉2
上記の文章を書いた後に、さらに補足したほうがいいと思ったことを以下に書きます。
伊藤悟様
私はこの事件が起こる約二ヶ月前に、あなたの著書にまとめて目を通す機会がありました。ちょうどホモセクシャル関係の文献をあさっていたときのことです。近所の図書館にはほとんどなかったのに、実家の近くの図書館にはいろいろそろえてありました。滞在期間が限られていたので、ほとんど夜を徹する勢いで読破しました。参考までにそのとき読んだ本の書名を挙げます。
「男ふたり暮し」 伊藤悟 (太郎次郎社) 1993
「ゲイ・カップル 男と男の恋愛ノート」 簗瀬竜太&伊藤悟 (太郎次郎社) 1994
「同性愛の基礎知識」 伊藤悟 (あゆみ出版) 1996
「同性愛者として生きる」 伊藤悟 (明石書店) 1998
このいずれかの中であなたは「足を踏まれたら、痛いと言っていい」(正確な文章ではないかもしれません)とかいておられたような気がします。これについては異存はありません。また「泣きながら抗議してもいい」とも書いておられたような気がします。これもOKです。ですから週間金曜日の記事のタイトルに使われた「オカマ」という言葉が、あなたの引き金をひき、それによって傷ついた感情を金曜日に訴えたことについては、それなりに理解できることです。ですが、何故、それを同性愛者の一団体である「すこたん企画」の名のもとに行ったのか。まるでそれが同性愛者全般に関わる差別であるかのように振舞ったのか。百歩譲って、ご自身、その混乱に気づいていらっしゃらなかったのだとしましょう。そして…。
ここからは「週間金曜日」批判になります。なぜなら、彼らはその混乱を見抜けなかったからです。ある意味で辛さんの対応が一番素直なものだったのでしょう。傷ついたという感情に共感することはたやすいですから。誰しも傷は持っているものです。その部分を直撃され、ご自身の傷とともに揺れることは何ら非難されるべきものではありません。しかし共感度の高い個人としてはそれでよくても、編集委員というプロとしては???。
「差別」などなかったとしか私には思えません。そうである以上、「すこたん企画」さんの「抗議」が「抗議」として成り立つとも思えません。あれは「悲鳴」です。「三杯目」という言葉を聞いたときに義母が発した悲鳴を私が思い出したのはきっとそのせいでしょう。「悲鳴」は挙げていいのです。というか、挙げていいだの何だという前に、ほとばしるのが「悲鳴」というものの本質です。
誤解を招くといけないので、付け加えておきますが、「三杯目」という言葉と「オカマ」という言葉を同列に考えているわけではないのです。私がこれを出したのは、「差別」と「トラウマ」は別物だということを示す上で、わかりやすい事例だと思ったからです。
私の感じ方は間違っているでしょうか。セクシャルマイノリティの気持ちもわからない、バカノン気の独り善がりでしょう。ですがそう解釈すると、その後の伊藤さんたちの振る舞いにも一本筋が通るような気がするのです。つまり、あれは「同性愛者差別への抗議」という形態をとった「すこたん企画」さんと、そのお友達の「週間金曜日」さんの内輪げんか。その喧嘩に他人なんて必要ありませんよね。及川さんの呼びかけにも、松沢さんの呼びかけにも、そして伏見さんの呼びかけにも応えなかった伊藤さんの真情が少しは見えてくるような気がするのです。
でも、それでいいの、伊藤さん。傷ついていい、泣いてもいい。でもそれと差別と戦うのは同じでしょうか。というか、それが有効な戦略でしょうか。
及川さんの記事を読んで私は勇気付けられました。同性愛者の方々とはまた感動する焦点が違うかもしれません。物ごころついたときから私は「変な子」でした。そしてそのまま「変な女」になり、今に至っています。
週間金曜日「オカマ」問題についてまわる、もやもやしたわけのわからなさ。それをきっかけにして伏見さんのとった対応は見事なものだったと思います。伊藤さん、伏見さんの「愛」を感じませんか。伏見さんは呼びかけているのです。
「何を一人で傷ついているの。でておいで、話し合おうよ」と(こんな優しくない?よろしければ、オネエ言葉に翻訳して読んでください)。
実家の近くの図書館には「パレード」の本もありました。私がそれを読み終わったのは、奇しくも2001年度のパレードが行われる前日でした。この符合に私の胸はときめきました。いつか参加できたらいいなあ。でも、子供が大きくなってからね(私にはもうじき学齢期を迎える子供がいます。学校での「いじめ」の問題は他人事ではないのです)。。
|